『〇〇パフェ』 作:塚田浩司

『〇〇パフェ』
お姉ちゃんとケンカした。
正直、ケンカの理由はもう覚えていない。だけど、頭にきている気持ちだけは体全体に広がっていた。
むしゃくしゃした美咲は家を出た。お姉ちゃんの顔なんか見たくなかったからだ。
ムカムカしながら歩いていると、喫茶店のショーケースが目に入った。美咲は近寄り、ショーケースにおでこと手を当て、中の食品サンプルに見入った。そこには、まるで本物みたいなコーヒーやメロンソーダ、オムライスに、スパゲティナポリタンが飾られていた。その中でもフルーツパフェに目が釘付けになった。そのパフェは、イチゴやバナナ、メロンやブドウがのっていてまさに美咲の理想とするパフェそのもの。見ていると胸が高鳴った。
こんなパフェ一度でいいから食べてみたい。美咲の口の中に唾液がたまってくる。見ていると怒りが治まってきた。
パフェと言えばお姉ちゃんがよく作ってくれる。パフェと言っても、プラスチックの透明なコップにコーンフレークを入れて、その上にバニラアイスと、ご近所さんからもらったりんごをのせただけの、あんまり可愛くないパフェだ。
せっかくショーケースの豪華なパフェを見ているのになぜかお姉ちゃんの貧相なパフェが思い浮かんだ。お姉ちゃんを思い出したらまたイライラしてきた。
でもふと思った。こんなお店今まであっただろうか。建物を見ると古めかしくて柱から屋根の上にまで蔦の葉がはっている。こんな古い建物が突然建つわけがない。不思議に思っていると、お店のドアが開きドアベルの音がカランカランと鳴った。美咲は驚き、慌ててショーケースから手を離した。
「いらっしゃいませ。さあお入りください」
そこには、ベストに蝶ネクタイ姿の、髭を生やした男の人が立っていた。
「あっ、あっ、お客さんじゃないです」
美咲はおそるおそる答えた。お店に一人で入るなんてできるわけがない。
「そうですか。でも、もしよかったらどうぞ。お金のことなら大丈夫です。お子様からは頂かないことになっていますから」
「えっ、そうなの?」
「はい。さあ、どうぞお入りください」
男の人は優しい笑顔を浮かべた。
本当だったら知らない人についていってはいけない。それは学校の先生やお母さんから教わった。だけど、この男の人の笑顔があまりにも優しそうで美咲は吸い込まれるように店の中に入った。
「あの、おじさん。本当にお金なくてもいいんですか?」
「はい。大丈夫です。それよりお客様、私はおじさんではなく、マスターです」
マスターはウインクした。
「さあ、こちらへお座りください」
マスターは椅子をひき、その椅子に美咲は腰をおろした。美咲はテーブル席に着くと、店内を見渡した。店内は木のぬくもり溢れる内装で、観葉植物がたくさん置かれており、まるで森の中のようだった。とても素敵な雰囲気だけどお客さんは一人もいない。
「こちらがメニュー表です。お好きなものをご注文ください」
マスターがメニュー表を美咲に手渡す。
美咲はドキドキしながらメニュー表に目を落とした。
そこには、コーヒー、紅茶、サンドイッチやチーズケーキ、いろんな飲みものや食べ物が書かれていた。だけど美咲が気になるのはもちろんパフェだ。
「あった」
美咲はメニューの中からパフェを見つけた。でも、おかしい。そこにはチョコレートパフェでもフルーツパフェでもなく、〇〇パフェと書かれている。
「あの、〇〇パフェってなんですか?」
美咲は目を丸くしながらマスターに尋ねた。
「こちらは、当店の看板メニューです。なんと、このパフェはその方が思い浮かべる理想のパフェなんです」
マスターは得意げに言うが、美咲にはまったく意味がわからなかった。
美咲が絶句していると、
「こちら召し上がってみませんか?」とマスターが言った。
どうしよう。意味はわからないけど、パフェだしな。
「はい。お願いします」
美咲が言うと、マスターは「かしこまりました」と頭を下げて席を離れた。
それにしてもどういうパフェなんだろう。楽しみ半分、怖さ半分だった。
席を離れたマスターはすぐに美咲の席に戻ってきた。そして「おまたせしました。〇〇パフェです」と言ってパフェグラスを美咲の前に置く。
ワクワクしながら見たけど、パフェグラスの中は空っぽだった。
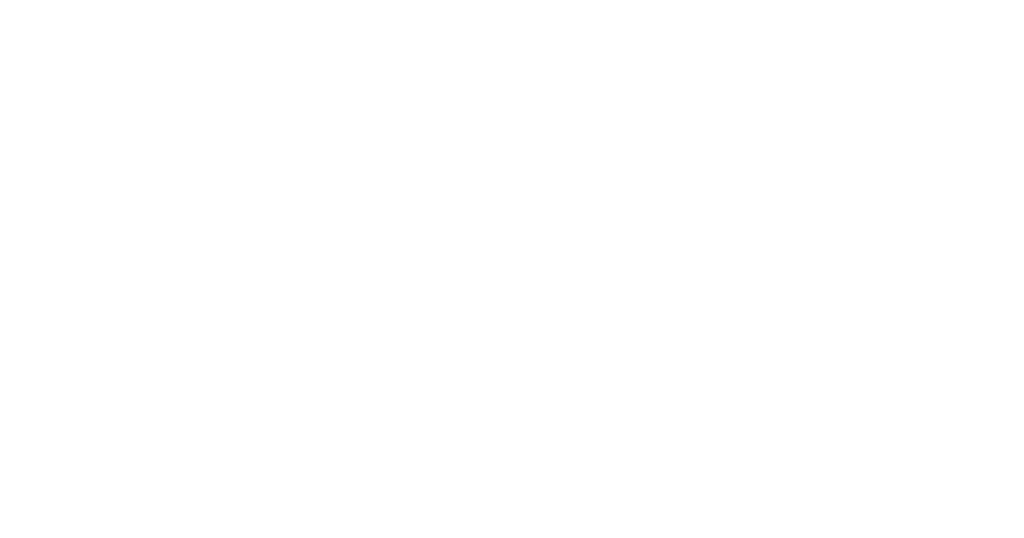
「あの、これ?」
美咲は困惑した。
「こちらを作るのは、お客様です。いいですか、よく聞いてくださいね。まず目をつむってください」
美咲は言われた通り目をつむった。
「そして、食べたいパフェを思い浮かべます。どんなものでもいいんですよ。苺でも、チョコでも抹茶アイスでも、パイナップルでもお望みのパフェをイメージしてください。そうしてから目を開けるとお客さんの目の前ある空っぽのグラスの中に、理想のパフェが出来上がっています」
本当かな。そんな魔法みたいなことがあるのだろうか。それでも、真っ暗の中、美咲は自分の食べたいパフェを思い描こうとした。やっぱりパフェにはフルーツをいっぱいのせたい。できるだけ豪華に、カラフルにしたい。
だけど、おかしいな。豪華なパフェを思い浮かべたいのに、頭の中にはお姉ちゃんが作ったコーンフレークとアイスとりんごだけのパフェしか浮かばない。なんでなの。どうせならたくさんのフルーツが敷き詰められた可愛らしいパフェがいい。理想のパフェが思い浮かばずに困っていると、
「お客様、パフェが出来上がりましたよ」
マスターが言った。その声で目を開けると、目の前には想像していた通り、お姉ちゃんがいつも作るパフェが置かれていた。
「さあ、召し上がれ。それにしてもずいぶんとシンプルなパフェですね」
マスターはシンプルと言ってはいるけど、本音では貧乏くさいと思っているはず。こんなパフェをマスターに見られることだけでも恥ずかしかった。
「これ、お姉ちゃんがいつも作ってくれるパフェなんです」
美咲は憮然とこのパフェの説明をした。
「へえ、それはステキなお姉さまですね」
マスターが感心したように言ったけど美咲は何も答えなかった。
「さあ、アイスが溶けてしまいますのでお召し上がりください」
マスターが言うので、美咲は仕方なしに細長いスプーンを手に取った。そして、パフェを口に運んだ。うん、やっぱりいつもの味だ。
「お味はいかがですか?」
マスターが訊いた。
「普通です」
美咲は不愛想に答えた。
「そうですか。ところでお姉さんはこのパフェをどういうときに作ってくれるんですか?」
どういう時? どういう時だろう。美咲は考えた。
そういえば、お姉ちゃんがパフェを作ってくれるときは決まって美咲が落ち込んでいる時だ。特に印象的だったのは学校で仲の良い友達とケンカしてトボトボと家に帰ると、お姉ちゃんが「美咲、パフェ食べる?」と聞いてくれた。美咲はもちろん「食べる」と答える。お姉ちゃんの可愛くないパフェを食べていると嫌なことも忘れられた。
お姉ちゃんのことを考えていると、いつのまにかパフェを完食していた。
「おっ、キレイにたいらげましたね」
マスターが嬉しそうに言った。その笑顔を見て美咲は口を開いた。
「あの、マスター、さっきは普通って言ったけどパフェ美味しかったです」
実際にそのパフェは美味しかった。それに、冷たいのに温かい味がした。
「そうですか。それは良かったです。あっ、もうお帰りですか?」
立ち上がった美咲にマスターが言った。
「はい。はやく家に帰らなきゃいけなくて」
「そうですか。では、どうもありがとうございました」
頭をさげるマスターに美咲は「ごちそうさまでした」と声をかけ、急いで店を出た。
家に向かって走りながら思った。ケンカといっても本当は自分のわがままなんだ。お姉ちゃんは何も悪くない。ただイライラしてお姉ちゃんに八つ当たりしていただけなんだ。早くお姉ちゃんにごめんねって言わなきゃ。
全力で走ったから美咲が家に着くころには息がぜえぜえしていた。
玄関の扉をあけて家に入る。お姉ちゃんは居間でテレビを見ていた。
「ねえ、お姉ちゃん」
声をかけると、お姉ちゃんは「ああ、おかえり」と言った。さっきのことがあったからお姉ちゃんの顔がどことなく暗い。
「お姉ちゃん、そのっ」
どうしてだろう。ごめんの言葉が出てこない。こんなときにどうして素直になれないんだろう。そんな自分が嫌だ。すると「あっそうだ」とお姉ちゃんが口を開いた。
「ねえ、美咲。パフェ食べる? お姉ちゃんパフェ食べたくなっちゃった」
「うん」
さっき食べたばかりなのに反射的に答えた。
「うん。わかった」
お姉ちゃんは立ち上がり、台所に向かった。
美咲はお姉ちゃんの背中に小さな声で「ごめんね」と声をかけた。

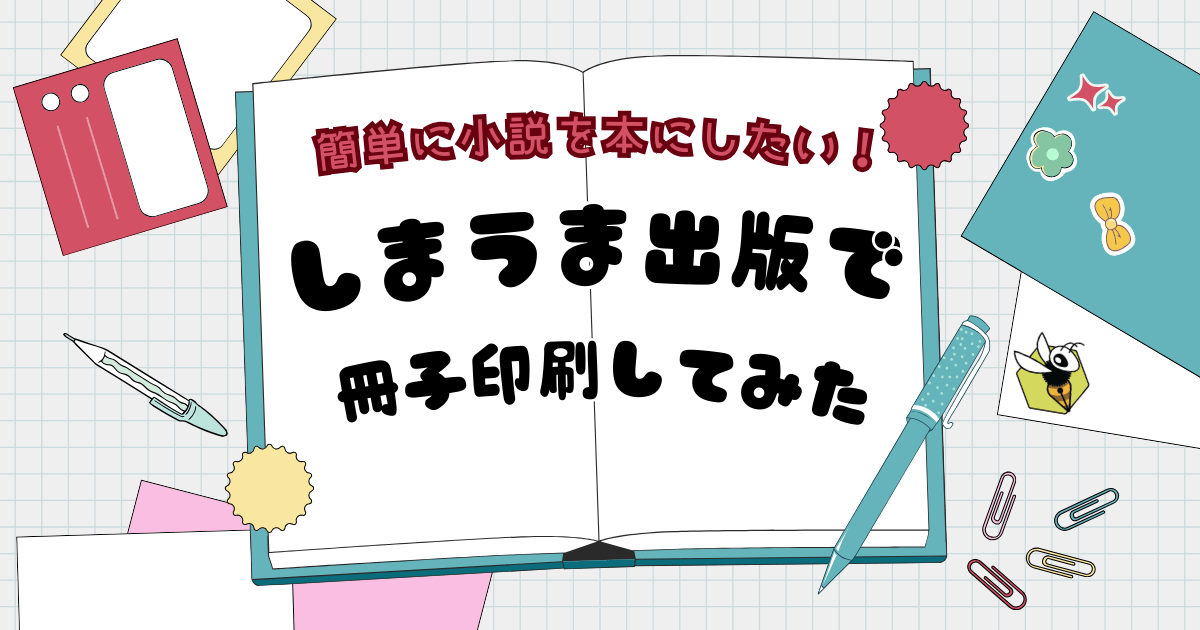


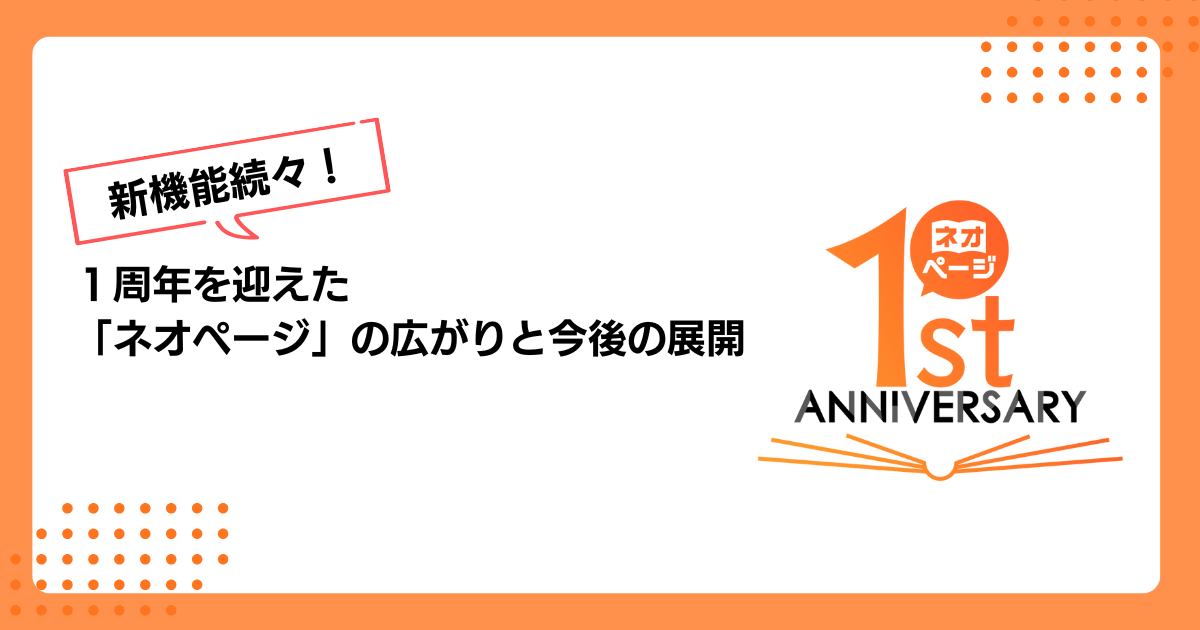
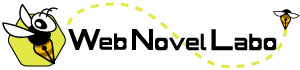




コメント