『サプライズ・メニュー』 作:酒本 歩

『サプライズ・メニュー』
『必ず来てくれよ、父さん』と言われた。
私は坂道を登ってきたので少し汗ばんでいる。その純喫茶は丘の上にあった。こんな店に呼び出してなんの用なのか。一人息子の祐太は就職してから、この街で一人暮らしをしていて、今年二十八歳になる。
私はこの春に定年を迎えたが、会社と再雇用契約を結んだ。まだ老け込むつもりはない。祐太には駅からタクシーを使うように言われたが、ちょうどいい散歩だと思って歩いてきた。かかりつけ医にも毎日できるだけ歩くように言われている。
ドアを開けると品の良いマスターが出迎えてくれた。
「いらっしゃいませ。失礼ですが岩田様ですか」
「ああ、息子と待ち合わせなんだけど。ちょっと早く来てしまって」
「テラス席にご案内するようにと言われています」
外には見事なイングリッシュガーデンが広がっていた。つるバラや紫陽花がそよ風に揺れている。椅子に座るとニュータウンの街並みが見下ろせた。確かに景色は良い。
「ご注文をお伺いします」
白のワイシャツに蝶ネクタイを結んだマスターは、メニュー表をテーブルに置いた。
私はコーヒーの料金を見て目を剥いた。一番安くて五百円からだ。
「高いな」
思わず言葉になった。
「すいません、二杯目はサービスですので」
「や、失礼。あまりこういう店に来ないので。じゃあこの、本日のおすすめを」
「かしこまりました」
メニュー表にはたくさんのコーヒーの名前が並ぶが、マスターが今日の気温や湿度を考えて挽く豆が一番なはずだ。住宅街から離れているせいか、ほかに客はいない。私はコーヒーを楽しみに待ちながらメニュー表を眺めた。
※ サプライズ・メニュー ¥0
お客さまの運が良ければ
メニュー表の下に小さく書いてある一行に目を留めた。
サプライズで無料? なんだろう、これは。
「おまたせしました。本日のおすすめコーヒーです」
深みのあるかぐわしい香りが漂う。
「ありがとう。マスター、このサプライズ・メニューって?」
「それは秘密なんです。と言いますか、いつあるか私も分からないんです」
マスターはいたずらっぽく微笑んでカウンターに戻っていく。
私は首を傾げた。『お客さまの運が良ければ』とあるから、たとえば百人目のお客が来店したら、コーヒーが全員、無料になるとか、そういうことだろうか。
バラの絵柄が美しいカップを手にした。一口味わって、そのコクと余韻に夢中になった。インスタントとは比べようもない。
祐太が小学生の時に妻を病気で亡くして以来、私はずっと倹約に努めてきた。コーヒーは大好きだから毎朝飲んでいるが、スーパーで特売のインスタントコーヒーだ。喫茶店などもう20年近く入ったこともない。
「祐太のこと、お願い」
それが妻の最後の言葉だった。私は約束した。
仕事はきつかったが、真面目に働き、無駄遣いせずに貯蓄に励んだおかげで、祐太が希望した私大に行かせてやれた。無事に卒業し、名の通ったIT企業で勤めている今、私が心配しているのはひとつだけ。結婚話だ。
二か月ほど前、祐太から年上で子連れの女性と結婚したいと言われた。子どもは小学校に入学したばかりだと言う。
私が頭ごなしに反対したせいか、珍しく言い争いになった。私は穏やかな性格の祐太が一歩も引かずに、最後は涙までこぼしたことに驚いた。泣くほどに女性のことを思い詰めていたのだ。
それならばと私はその女性に会わせるように言ったが、相手の女性は結婚を承諾していないと言う。私は肩透かしを食ったような気分がした。そして急に腹立たしくなった。一人親だが祐太のことは、どこに出しても恥ずかしくないように育てたつもりだった。
よく話を聞くと、相手の女性は祐太が気に入らないのではなく、一度失敗した結婚というものに臆病になっているのだそうだ。しかし分かったものではない。祐太は金づるにされている可能性だってある。
祐太は今日もその話を蒸し返すつもりなのかもしれないが、認めるつもりはなかった。第一、相手の顔も見ずに賛成したら妻に申し訳が立たない。
ふと気がつくと外は薄暗くなっている。BGMがクラシックからスローなジャズに変わっていた。祐太に言われた待ち合わせの時間は過ぎている。私は電話してみようとスマホを出した。
前触れもなく、ドンと空気が震える音がした。顔を上げると薄墨をはいたような空に光の線が尾を引いて上がっていく。赤い大輪の花がぱっと開いて、鮮やかに空を彩る。一瞬遅れて、ドンという一層大きな音が響き渡る。

「花火だ……でかいな」
私は椅子から立ち上がり、突然始まった天空のショーに固唾をのんだ。
「お客さま、運がよろしかったですね。こちらがサプライズ・メニューです」
マスターが傍らに立った。
「すごいな。花火大会か何かかい」
「大会ではないんですが近くに花火工場がありましてね。最近、個人のオーダーで花火を打ち上げるようになったんです。どうです? サプライズでしょ」
「いや、ほんとに驚いたよ」
次々に打ち上がる花火は、天空で煌々と輝いては儚く消える。空は暗くなるいとまもない。
妻が入院する前、家の庭で三人揃って浴衣を着て、家庭用の花火を楽しんだことを思い出した。妻は花火が大好きで、本物の打ち上げ花火を一番前で見るのが夢だと言っていたが、病気がそれを許さなかった。
「個人のオーダーってことは、何かの記念日を祝うとかそういうことかな」
「そうですね。誕生日のプレゼントとか、会社の創立記念とか、いろいろあるみたいです」
「でもこの花火って相当、費用がかかるだろうね」
「ええ、最低でも20万円からだそうですよ」
「20万円……」
世の中には金が余っている人がいるものだ。
いきなり中空にピンクの色彩が弾けた。目の前でハート形に広がる。
「ああ、あのハートの花火が打ちあがると言うことは、もうプロポーズで決まりでしょうねえ」
「プロポーズ?」
「花火工場の近くにカップルがいるんですよ。この花火は君のために打上げてるんだ。僕と結婚してほしい、なんて言われたら、彼女の方は感激するでしょうね」
「しかしプロポーズに、こんな浪費をするなんて」
「まあ、プロポーズする男性にとっては一世一代の大勝負なんじゃないですか。よっぽど彼女に惚れてるんでしょう」
私ははっとした。
「まさか……」
祐太はこの店に私を招いておいて姿を見せない。私が案内されたのは花火を見るための特等席のようなテラスだ。
今、正にプロポーズをしているのは祐太なのではないだろうか。自分との再婚を躊躇っている女性に、自分の真剣な気持ちを伝えているのではないか。
「いよいよクライマックスです」
マスターが呟いた。花火のグレードが上がったのか、花が一回り大きくなり、花弁が開く位置も高い。連発だ。打ち上げる音、開花する音が太鼓を叩くように鳴り止まない。私は思わず手を握りしめた。
束の間の静寂。
ドーン。
振動が身体を揺さぶる。光の尾はどこまでも上がり、金色の花が天頂で夜空を覆う。火の粉が顔に降りかかりそうだ。眩い花びらはチリチリと音を立てて闇に消えてゆく。
「今のが最後ですね」
「えっ、もう?」
終わってみれば、ほんの数分間のショータイムだった。私はふうっと息をついて椅子に腰を下ろした。
空には何も無かったかのように星が瞬いていた。気の早い虫が鳴いている。
「マスター、それでプロポーズは成功したのかな」
「いやいや、それは私にも分かりませんけど……」
マスターは、ぽんと両手を打った。
「さて、コーヒーのお代わりをお持ちします」
スマホが震えた。祐太からのラインだった。
『ごめん、もうすぐ着くよ。花火、楽しんでくれたかな』
やはり祐太だった。続いてメッセージが表示される。
『今日、父さんと母さんの結婚記念日だね。おめでとう』
忘れていた。祐太はよく覚えているものだ。そう考えた私はふと思った。祐太がこの日を選び、花火でプロポーズしたのは、花火が好きな妻のためでもあったのではないだろうか。妻が空から見ていると思ったのではないか。
私は胸が突かれる思いだった。またスマホが震える。
『そこのコーヒー、美味しいだろ。たまにはちゃんとしたコーヒー、飲んでよ』
私はマスターが持ってきてくれたお代わりのコーヒーをゆっくりと味わった。
テラスの隣に見える駐車場に車が入ってきた。軽自動車の助手席から姿を見せたのは祐太だ。後部席を開けると小さな子どもが飛び降りた。やんちゃそうな男の子は、祐太と運転席のドアを閉めた女性の手を引っ張るようにしてこちらに駆けてくる。三人とも浴衣を着て笑っていた。どうやらプロポーズは成功したようだ。
私は男の子が、妻が生きていた頃の祐太と重なった。
まぶたが熱くなって目を固く瞑る。祐太があの二人と家族になりたいと思う気持ちが痛いほど分かった。
もう賛成だ、賛成。大賛成。
あんな幸せそうな姿を見せられたら認めるに決まってる。

<了>
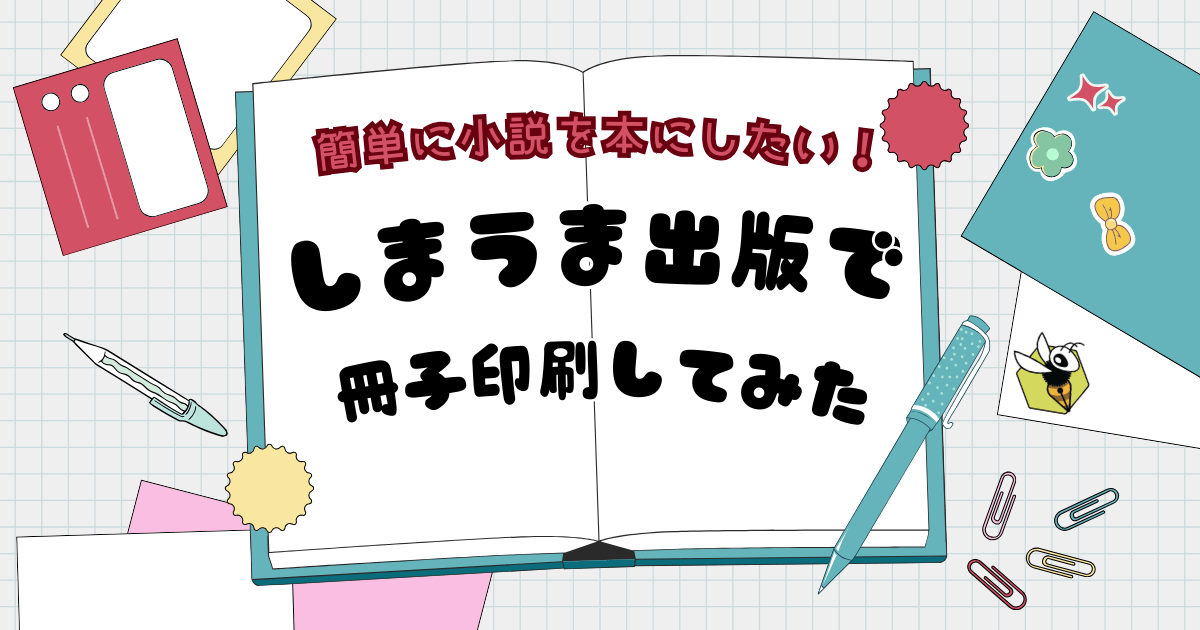


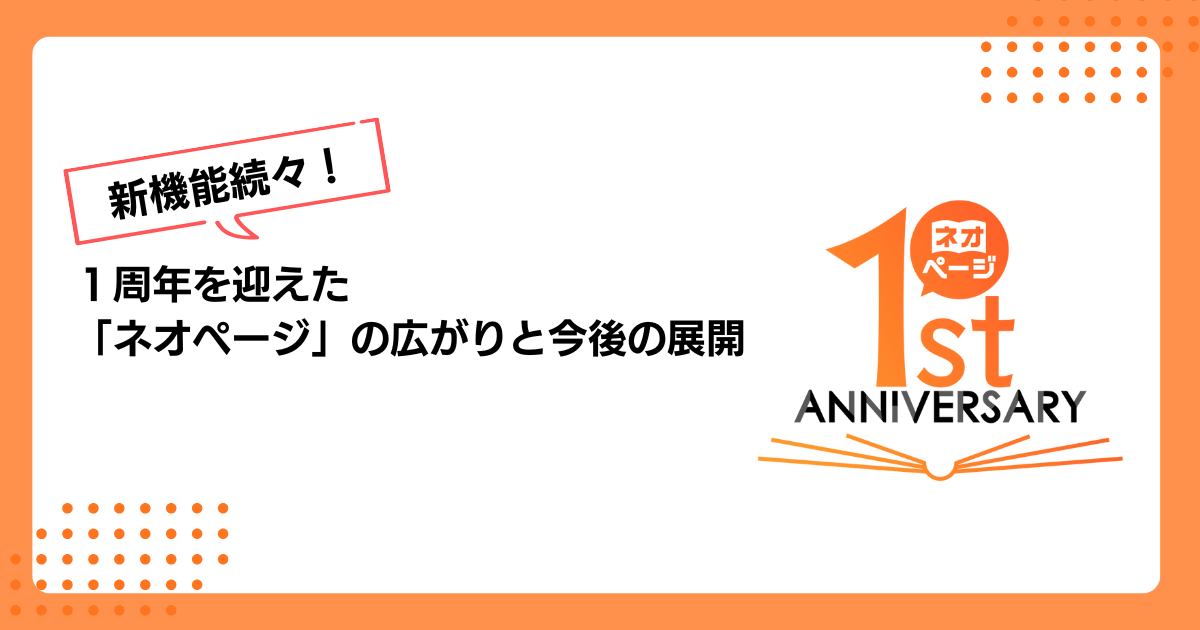
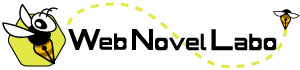




コメント