『人魚かもしれない』 作:椿あやか

ボクのクラスの
手足が魚みたいに冷たいとか。夏でも長袖なのは鱗を隠しているからだとか。夜中に一人で海を泳いでいるのを見た、脚が無かった――とか。
ボクは脚がないのは人魚じゃなくて幽霊じゃんか。などと心の中で大月を擁護した。
大月はクラスの女子の中で一番背が高く、大人びて、美人で、学校にネックレスとかつけて来ていてハッキリ言って浮いていた。
でも女子の中でボク――
***
明日から夏休みだ! という終業式の夜、宿題をまるごと学校に忘れてきた事に気が付いたボクは、夜の学校に取りに戻った。
そうして見てしまった。人気のないプールでひらひらとした尾ひれを優雅に動かしながら泳いでいる大月窓香を。
その下半身――脚の部分は青白い鱗で覆われていて、満月の光が反射してとても綺麗だった。
三階の教室の窓からボクが見ている事に気が付いたのか、大月はにっこりと笑って水面を叩くように跳ね上がるとプールの深い所へ潜って行ってしまった。
ボクはただうっとりとしてしまい、どうやって家まで帰ったのかは覚えていない。
それから一週間ほどした登校日の事である。 ボクの窓際一番後ろの席からすると大月の席は右縦にひとつ、前横にみっつ離れていたのだが視力2.0のボクにはその姿がよく見えた。 大月は普通に人間の女の子で、白地に水色の横縞模様のワンピースを着ていたがボクは思わず脚をジロジロみてしまった――やっぱり普通の人間の女の子だよなぁ。 あまりに見過ぎていたせいか、視線に気が付いた彼女は微笑みながらスーッと泳ぐようにボクに近づくと、こっそり耳打ちをしてきた。
「日下くん、この間の夜‥‥見たでしょ」
「見た。大月って、人魚だったの?」
あまりにストレート過ぎる質問だったのか大月は目を丸く見開いて、うふふと笑った。
「だったらどうする? 言いふらす?」
「言いふらさない。なぁ。どうやって人魚になったり人間になったり出来るのさ」
「知りたい?」
「知りたい」
内緒だよ――そう言って大月はいつもつけているネックレスのチェーンを服の中からたぐり寄せると、そのペンダントトップについた淡い水色にほんの少し翠がかった光沢の貝殻を見せてくれた。
「人魚貝っていうの」
「普通の貝に見えるけれど‥‥でも、綺麗だね」
「ありがとう。そう、人魚が結婚するまでは普通の貝なんだよね」
「どういう事‥‥?」
「日下くん、二枚貝ってどれも同じようにみえるけれどぴったり合わさる組み合わせって一つだけだって知っている?」
「聞いたことあるような無いような」
「人魚はね、女しかいないの。人魚に恋した男の人が人魚と結婚するには人魚と出会った土地の海辺で一番美しい貝殻を探してプロポーズするのがしきたりなんだけれど、きっとそうやって貝を渡すのは唯一無二の組み合わせに夫婦の永遠の愛の重ねているからなのかもね」
人魚貝を見つめる大月の頬が少し染まる。
「で、その時に人魚が結婚を受け入れたら普通の貝はその瞬間に海神さまの加護を受けて人魚貝となるの」
「えっ! 大月もう結婚しているの!」
「してない。してない。ちゃんと最後まで話を聞いて。人魚貝はね人魚に子供が生まれたらその子供に肌身離さず身に付けさせるの、そうして身に付けたまま水に入ると――」
「人魚になる!」
「あたり!」
大月がうふふと笑う。何だかこっちも嬉しくなる。
「すげぇなぁ。そんな事って本当にあるんだな変身できるって何か格好いいよ」
「そうでもないよ‥‥」
さっきまで笑顔だった大月の顔が曇る。
「どうかした? ボク、なんか変な事言っちゃった?」
「ううん。人魚の子はね、十二歳から大人とされていて――つまり私も十二歳までに人魚として生きるか人間として生きるか決めなくてはいけないの」
「誕生日、いつ?」
「八月の‥‥ちょうど次の満月の日」
「結構すぐだね」
「うん」
「どうするの」
「どうしよう‥‥でも決めないとさ、童話にあるでしょ。泡になって消えちゃうやつ。ああなるんだって」
「そうか‥‥」
大月の話は壮大すぎて正直ピンと来ない所もあったけれど、ボクは出来れば人間になる方を選んでもらって一緒に卒業したいなと思った。
***
夏休みに入ってボクが連れて行って貰えたのは近くの浜辺だけだったけれども、大月の話のせいか今年は貝殻を観察したりシーグラスを拾ったり、きれいなものは幾つかズボンのポケットに入れて持ち帰ったりもしてそれなりに楽しめた。
ボクは夏休みの宿題をコツコツこなし、休みもじわじわ減っていき、毎日の昼食にそうめんが続く事に飽き飽きしはじめていた。
そんなある日の昼下がり。八月の満月の日‥‥つまり大月の誕生日の事である。
「陽介ー。女の子から電話よ。大月さんだって」
母さんがニヤニヤしながら電話をかわってくれた。早く自分用の携帯が欲しい。
そしてなんで大月が? 頭の中は「?」だらけだったがともかく電話にでると
「日下くん。どうしよう‥‥人魚貝、プールの中に落としちゃった」
「え。だって今日誕生日でしょ。無くしたまま誕生日を終えるとどうなるの」
「アレが無いと海神さまに意思が伝わらない。つまり何も伝えないのと同じになるから、たぶん――」
大月が泡になって消えてしまう。
ボクは学校へと走った。
既にプールの中に大月は居た。フェンスを乗り越えて入ろうとするボクに、フェンス同士をとめているボルトが緩んで半開きになる場所を教えてくれた。
「大丈夫? 警備員さんに言って一緒に探して貰おうよ」
「大ごとにしたくないの」
「だって、大ごとじゃないか!」
「ごめん。でも‥‥お願い」
いつも大人びている大月が今にも泣きそうだったので、ボクは従う事にした。
「いつも通りなら八時まで見張りは来ないはずよ」
ボクは服の下に一応水着を着ていたけれど、大月は服のままなのでそれに習ってTシャツだけ脱いで下は短パンのまま二人で潜水し、水中に目をこらす。
探せども探せどもみつから無い。
水中眼鏡でも持ってくればよかった。
――ずいぶんそうして居ただろう。
すっかり日が傾き、空が切ない色を帯び夏といえどもさすがに歯の根がかみ合わなくなった頃。
「おい! 窓香! 何をやっているんだ」
顔を上げると目元が大月と似た線の細い男の人が立っていた。
警備員さんに借りたのか堂々とフェンスの鍵を開けて入ってくる。
「お父さん‥‥」
「帰るぞ。帰って引っ越し準備の続きだ」
――引っ越し?
「ま、待って下さい。大月は人魚貝をプールに落としてしまって大変なんです。このままだと人魚にも人間にもなれずに‥‥」
「人魚? 君は何を言っているんだ」
――え?
「だっておじさん、大月のお母さんに人魚貝あげたんでしょう?」
「貝? ああ前の――あの子の母親と出会った時にそんなものもあげたっけな」
ドポン。大月のお父さんがプールに飛び込み、大月を追いかける。
「窓香、転勤は会社の都合で仕方ない事なんだ。おばあちゃんと二人でここに残るだなんて無理に決まっているだろう」
「お父さんなんて大嫌い! お婆ちゃん良いって言ったもん。友達もやっと出来たのにまた転校だなんて嫌!」
陽が落ちる――大月の足元がキラキラと泡立ちはじめる。このまま大月は消えてしまうのだろうか? それとも人魚だなんて嘘だったのだろうか? でもあの日見た大月は確かに人魚で‥‥大月にとってボクはただの友達だったのだろうか? 色々な考えがぐるぐる脳内を駆け巡る――。
いや、ボクは誓ったじゃないか大月に何かあった時は絶対に味方でいようって。
大月がプールから引き上げられる。その足元は半透明に透けている。人魚貝を身に付けていないのに腕を掴まれ、連れて行かれてしまう。
ボクの前から消えてしまう。
どうしよう。どうしよう。ボクはどうすればいい?
「日下くん、助けて!」
大月の声に我に返ったボクは無意識にポケットに手を入れた。手に何かがあたる。
「大月! おおつき!」
ボクははじかれたように走り出す。
かけっこは得意なはずなのに息が苦しい。
胸が痛い。
この気持ちは何だろう。
校門の近くまで行ってしまった二人にようやく追いついて、肩で呼吸をする。
「大月、これ受け取って」
ボクは海辺で拾った白い小さな桜貝を差し出した。
大月の大きな瞳は更に大きく見開かれて、その深い夜の海みたいな色合いの瞳にボクがはっきりと映ったかと思うと、ゆらりと滲んで彼女のほほを伝い落ちた。
「日下くん、これって‥‥」
「海で拾ったんだ。今日からこれが大月の新しい人魚貝じゃ‥‥だめかな」
彼女の白い手に握られた人魚貝が炎のように一瞬青くゆらめいた。
「‥‥ううん。今までのよりこっちの方がずっと、いいよ」
大月の脚は、もう透けていなかった。
長かった夏休みが終わろうとしている。
大月窓香は人魚だったかもしれないし違ったかもしれない――でも、今もボクの隣に居て、微笑みかけてくれている事は間違いない。
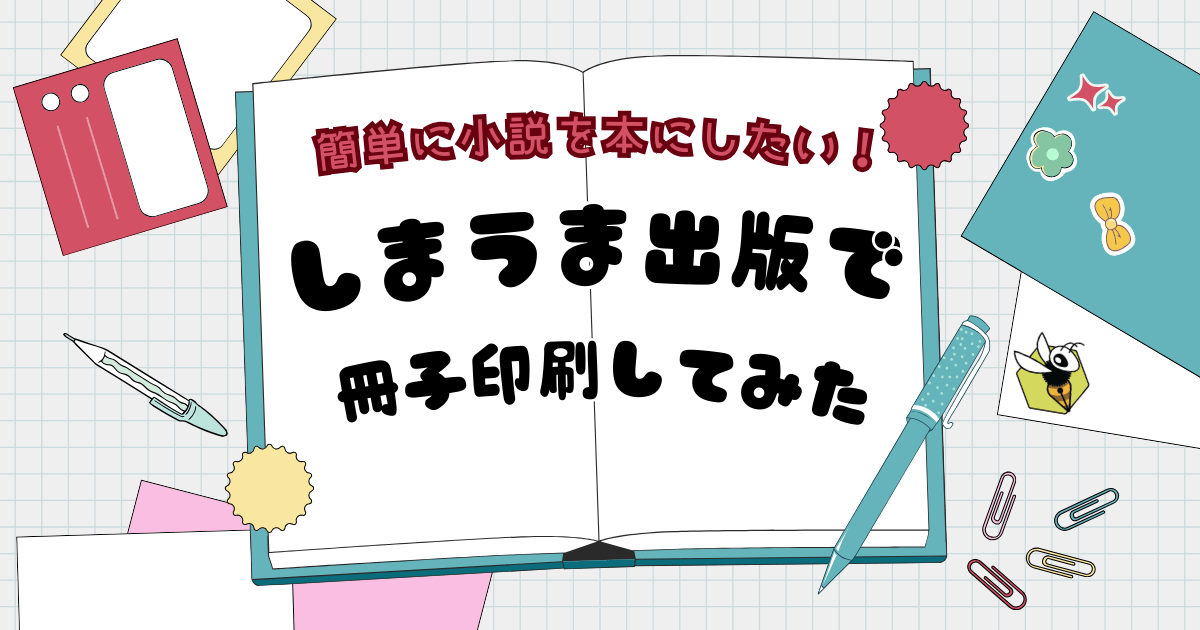


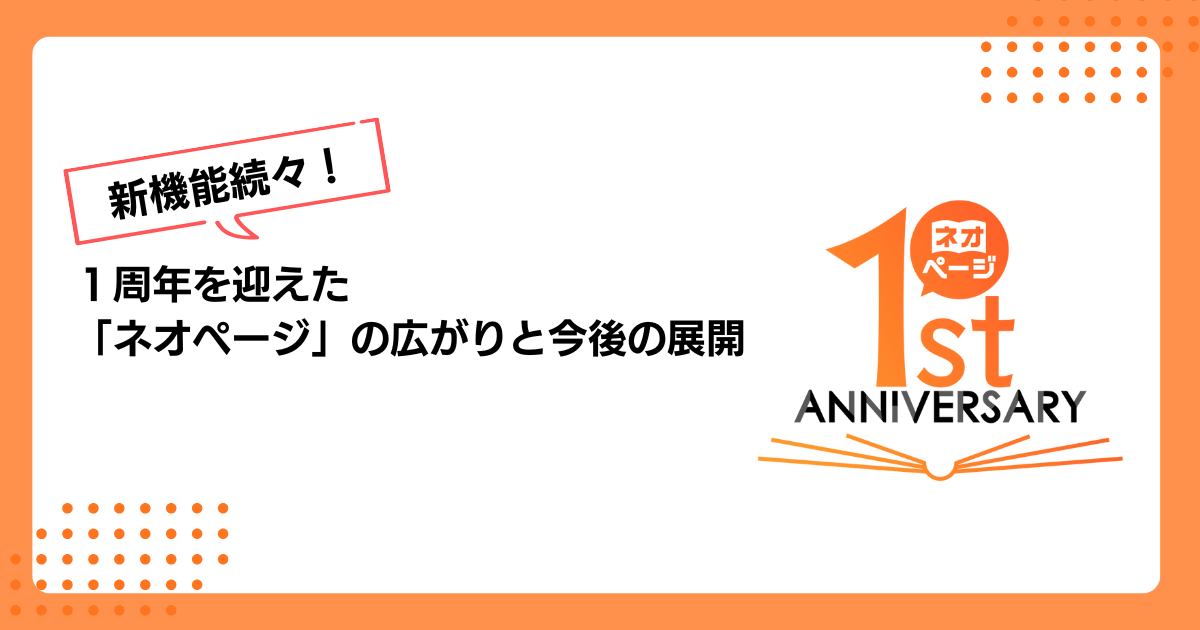
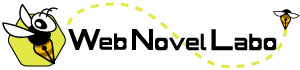



コメント