『時の彼方のレトロプリン』 作:秋田柴子

『時の彼方のレトロプリン』
――あら、プリン。まあ珍しいこと。
プリンなんて長いこと食べてないわねえ。まだ子供たちが小さい頃は、よくせがまれて買ったものだけど。
プリンといえば、最近のものはずいぶん感じが違うのね。前にお嫁さんが買ってきてくれたけど、洒落たガラスの瓶に入ってて、まるでクリームみたいにとろっとろなんだもの。驚いちゃったわ。
私、プリンと聞いてぱっと思い浮かぶのは、やっぱりあの富士山みたいな形でてっぺんがカラメルの、あれなのよ。正直言って今のとろとろしたプリンは、食べた後にどうにもお口の中がベタつくような感じがして……いえ、美味しくないってわけじゃないんだけど。だって孫は喜んで食べてたものね。
「恵梨はここのプリンしか食べないんです。他のお店のものは美味しくないからイヤなんですって」
お嫁さんが自分の娘の顔を覗き込みながら、嬉しそうに教えてくれて。
そう、今の子は舌が肥えてるものね。まあ親が買い与えるから、子供の方も小さいうちからそういう味を覚えるんでしょうけど……なんて、とても口には出せないわ。今の時代、お嫁さんに何か言えばすぐに「お義母さんは口出ししないで下さい」なんて言われちゃうもの。我慢、我慢ね。
でもね、本当のことを言うと、私は昔のプリンの方がずっと好きなの。
今のはそれこそとろっとした柔らかいのが多いんでしょうけど、昔のプリンはね、もっとぼってりしてて固かったの。お口に入れると少しざらっとしてて、ぷつぷつした空気の穴の感触がよぉく判るのよ。それが舌の上でほろりと溶けると、ちょっと焦がした風味のカラメルが甘くからんで……それはなんとも贅沢な味わいだったわ。
今じゃそんなプリン、なかなか食べられなくなっちゃったわね。
――よく覚えてるって?
ふふ、実はね。よく主人と行ったの。そう、結婚する前に。
お見合いしてもうほとんどお話は決まってたんだけど、一応ちょっとお付き合いを、っていう頃に何度か連れてってもらったの。あの人のお気に入りのお店、昔でいう純喫茶ね。まだ嫁入り前の娘だったから、そんなところ行ったこともなくて、ずいぶん緊張したものよ。
でもそこはとても素敵なお店だった。床もテーブルも落ち着いたシックな色合いで、大きな窓にかかった白いレースのカーテンが外からの風にふわんと揺れてね。だってその頃はクーラーなんてなかったもの。どこのお店でも窓は開けてあったのよ。
お店の中はいつも上品な音楽がかかってたわ。あの人はクラシックが好きだったから「これはバッハだ」「さっきのはモーツァルトだ」っていろいろ教えてくれたんだけど、私は全然判らないものだから。いやね、恥ずかしい。
あら、何のお話だったかしら……そうそう、プリンね。
そうなの、そのお店でプリンを食べたの。だって珈琲は苦くて飲めなかったし、ミルクじゃ子供みたいでしょ。そしたらメニューに「プリン・アラモオド」って書いてあったから、何だかちょっとお洒落かしらって。
でもお店のご主人がうやうやしく運んできてくれたのを見て、びっくりしたわ。
ぴかぴかに磨かれた銀色の器に、お手玉みたいな大きさのプリンがでん、とのってるんだもの。

その大きなプリンのてっぺんから、琥珀色のカラメルがつうぅとつたって器の底にたっぷりと溜まっててね。裾には生クリームがお花みたいに飾られてて、真っ赤なサクランボが……ああいうのはチェリーっていうの? そのチェリーがちょこんと添えられてたわ。ね、素敵でしょう?
食べるのがもったいなくてあちこちから眺めてたら、あの人が向かいから笑うの。「加奈子さん、いつまでも見てないで早く食べなさい」って。
今の若い人なら、ささっとお写真撮るのよね、きっと。いいわね、その頃はそんな便利なものもなかったから。
でも写真がなくてもよく覚えてるわ。あの人と一緒に食べたプリン。結婚して子供が産まれてからは、忙しくてほとんど行くこともなくなっちゃったけど。
ああ、懐かしい。あのお店、今でもまだあるのかしらね……
――あら、ごめんなさい。私、すっかり長話しちゃって。もうこんな時間? 大変、早く帰ってお夕飯の支度しなきゃ。もうすぐ子供たちも帰ってくるし、主人も七時前には帰ってくるから……
「あら加奈子さん、どこに行くの? もうすぐごはんですよー」
え? だめよ、帰らなきゃ。私が帰らないとごはん作る人、だぁれもいないんだもの。みんなお腹空かせて……
「加奈子さん、加奈子さん。そっちじゃないですよ。ごはんは食堂で食べますからね。お外はまた明日。ほら、明日はお散歩の日だから、一緒にお出かけしましょうね」
え、なあに? どういうこと? じゃあ、主人や子供たちのごはんはどうするの?
「きっとおうちのことが心配なのね……大丈夫よ、加奈子さん――そう、みんな今日は遅くなるって、さっき連絡がありましたよ。先に食べて休んでいいよ、ってね」
みんな帰りが遅いの? まあ、そうなの。知らなかったわ。最近は子供たちも大きくなったから忙しいのね……それなら先にお夕飯頂こうかしら……あら、どなたが作って下さったの? いいのかしら、こんな贅沢させてもらって。じゃあ遠慮なく頂きます……ああ、美味しい。ありがたいことねえ。
あの人も子供たちも、ちゃんと食べてるかしらね……
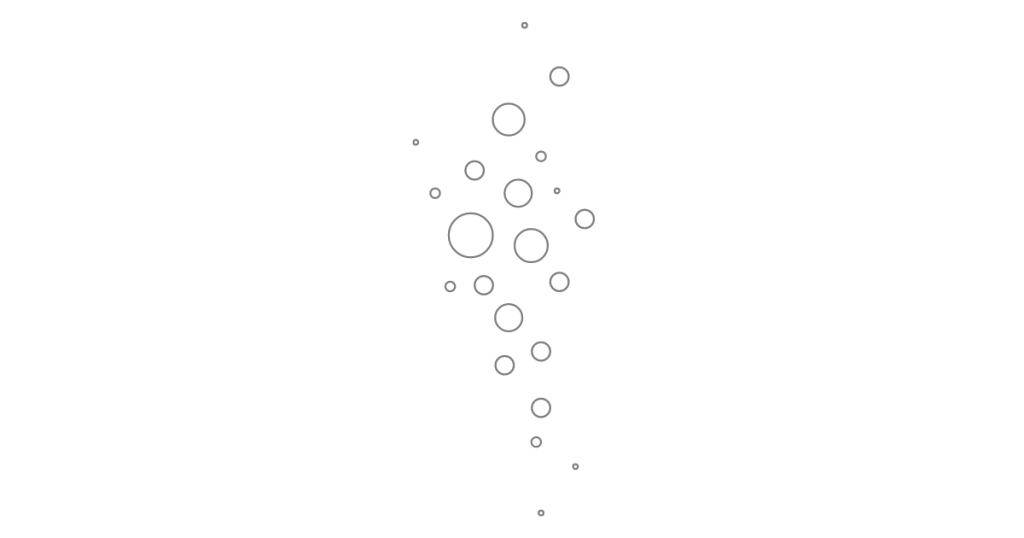
その日の夕食のデザートはプリンだった。
おぼつかなくなった手先で、老婦人がゆっくりとスプーンを口に運ぶ。ときおり口元からこぼれ落ちるぷるりとした固まりを、担当の若い男性スタッフが温かい笑みを浮かべて、そっと拭う。
「よかったね、加奈子さん。プリン大好きだもんね――よし、もう全部食べたかな。じゃあ、お部屋に戻ろうか」
青年は、自分の肩にも届かない小柄な老婦人の手を取ると、もう片方の手で細い肩を支えるようにして歩き出した。
すぐ隣に青年がいることも意識から抜け落ちてしまった様子で、ふんふんと幸せそうに口ずさむ老婦人の歩みは遅い。食堂から彼女の居室までは、若い青年の足ならほんの数秒でたどりつける距離だろう。だが彼は焦れる様子もなく、あたかも彼女の体の一部になったかのように、一歩ずつ歩みを進めていく。
「そうそう。上手だね、加奈子さん。ゆっくりでいいからね」
青年は、老婦人の手を軽く握るようにして笑いかけた。
いいのだ、たとえ何分かかろうとも、この人はまだ自分で歩くのだから。
自らの意思のもとに、自らの足で歩けるのだから。
「――はい、お部屋に着いたよ、加奈子さん。ちょっとここに座って休んでて。また後で歯磨きの時に来るからね」
だが青年がドアのところで振り返ると、老婦人はお気に入りの椅子の上で、早くもうとうとと舟を漕ぎ始めていた。
「あららら。風邪引くよ、加奈子さん」
慌てて部屋の中に戻ると、青年はそばにあった淡い緑色のカーディガンをそっと老婦人の肩に着せかけた。
やれやれと顔を上げると、すぐ後ろのチェストの上に飾られた古い写真が目に入る。くすんだ木製のフレームの中で、優しげなしわの刻まれた男性が、不器用な微笑みの奧からこちらを見つめていた。
「すっごく仲良しだったんだってね、加奈子さん」
青年は色褪せた写真に向かって軽く手を合わせると、まどろむ部屋の主を起こさないよう足音を忍ばせて、静かに部屋を出ていった。

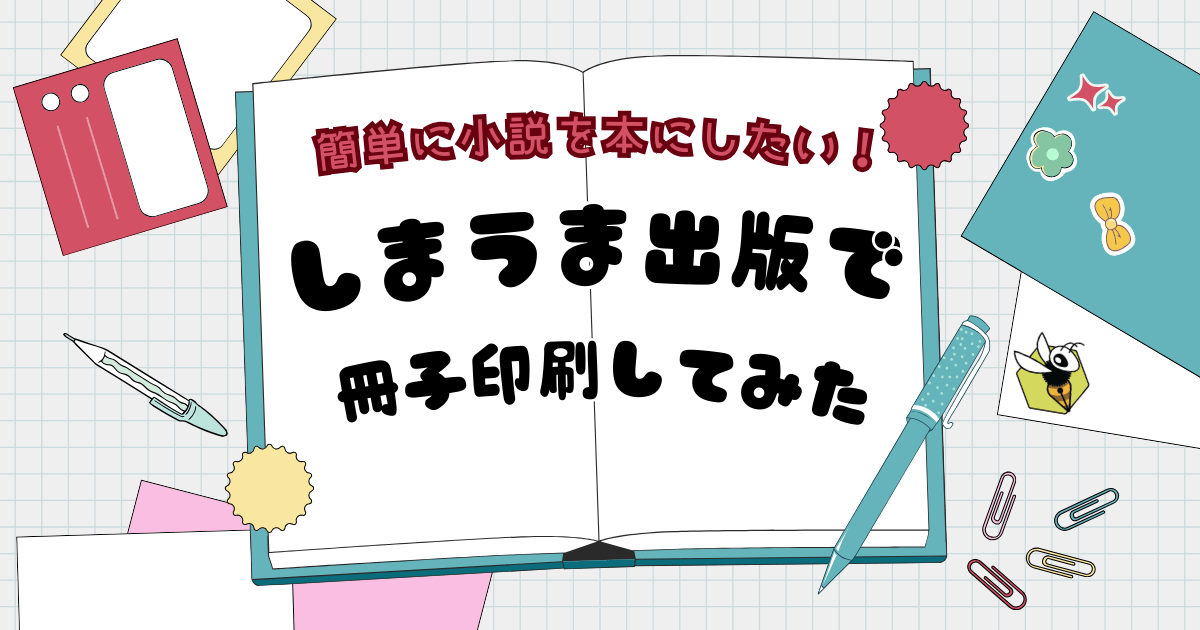


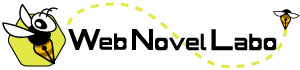




コメント