『量子の中の幽霊』 作:千吉

その研究所は人里離れた山の奥にありました。「量子力学」という学問を研究するところで、周囲の環境の影響を受けないように、地下の深くに作られておりました。幾重もの壁に覆われた数多くの実験室が、最新の機材と共に設えられています。高名な学者たちが大勢、ここに招かれまして、日夜、森羅万象の神秘を解き明かそうと、研究に励んでいたのです。
ところがいつの頃からか、地下の実験室で奇妙な事が起こる、という噂が囁かれるようになりました。
最初は、閉めたはずのドアがいつの間にか開いているとか、夜中に壁を叩く音がする(もちろん、厳重な研究所ですから、おいそれと隣の部屋の音が聞こえてくる事などありえないのです)、というものでしたが、しだいに話は大きくなって、男のうめき声が聞こえる、誰もいないはずの廊下が水浸しになっている、壁に貼ったアインシュタインの写真の口から舌が伸びて、冷蔵庫のアイスクリームを舐める、などと不気味な噂が広がっていったのです。
そのうえ、これらの怪現象が、どうやら研究所の一番奥にある「シュレディンガー実験室」の周辺でばかり起きていると知って、流石に精鋭揃いの学者たちも動揺を隠せませんでした。
シュレディンガー実験室と申しますのは、お察しの方もおいででしょうが、あの「シュレディンガーの猫の実験」を行うために作られた実験室だったのです。
ああ、何と恐ろしい言葉でしょう! シュレディンガーの猫の実験!
それはミクロな世界での電子の性質を証明するための実験でした。ミクロの世界では、私たちが見ているマクロの世界と違って、電子は、波の性質と粒子の性質の、ふたつの性質の両方を重ね合わせて持っています。その時の電子は、波の広がりのどこかに存在するのですが、どこに存在するかを特定することができません。電子の存在する場所は、電子を観測した時点で初めて決まるのです。私たちが電子を観測した時に、波がピュッと粒子の形に収縮して、電子として確認されます。つまり電子は、観測するまでは「どこにでも存在する」と言えてしまうのです。
しかし、観測するまで電子がどこにあるかわからないというのは、何とも気持ちの悪い状態です。
そこで、ある実験が考えられました。電子がどこに存在するのかわからない。どこにでも存在するのであれば、例えば、電子が場所Aに存在する場合と、場所Bに存在する場合が、同じ確率であったとします。鋼鉄で作られた箱を用意して、その中に猫を入れます。猫は三毛でも白でも黒でも構いません。観測した時点で電子が場所Bに存在した場合に、箱の中の猫を殺してしまう仕掛けを設置します。そして箱にフタをします。
するとこの場合、再びフタを開けて箱の中を見るまで、猫の生死は確定しない事になります。では、観測する前の、箱の中にいる状態の猫は、生きているでしょうか、それとも死んでいるのでしょうか。
仮説は「猫は、生きている状態と死んでいる状態を、重ね合わせて存在している」というものでした。そして、それを実証するために、実験室が作られたのです。
ああ、何と惨たらしい実験でしょう! 観測するまでわからないとはいえ、猫を殺してしまうなんて!
学者たちも、この実験室が完成して、自分たちのやろうとした実験の恐ろしさに気付きました。そして話し合って、このシュレディンガー実験室を封鎖する事にしました。以来、この実験室は、研究所の一番奥で「開かずの間」となっていたのです。
その開かずの間である実験室の周囲で、怪現象が起こるというのですから、研究所としても、このままにしておく訳にはいきません。
研究所の所長と屈強な研究員たち数名が、そのシュレディンガー実験室に入って、中を確かめることにしました。
ドアを開けた実験室は、機材が撤去されてガランとしていました。空気清浄機が働いておりますので、中は他の実験室と変わったところはありません。
一同は、その実験室で夜明かしをすることにしました。
しかし、夜の十二時になっても、何も起こりません。
研究員たちもだんだん気が緩んできました。午前一時を過ぎた頃には、居眠りを始める者もおります。
そして、草木も眠る丑三つ時。
突然、壁を叩く大きな音がして、うとうとしていた研究員たちは、はっとしました。すると、閉め切った実験室に生暖かい空気が吹き込んでくるではありませんか。どこからか、うめき声も聞こえてきます。皆が辺りを見回したその時、何も無いはずの実験室の壁から、一人の痩せた男がすうーっと部屋の中に入ってきたのです。
「トンネル効果だ!」
全員が色めき立ちました。波動となった幽霊が、物理的な障壁をすり抜けて、マクロの世界に出現したのです。
早速研究員たちは用意した機材で、原子核の崩壊や放出されるプロトンやニュートロンの観測を始めました。非番の研究員たちも次々と駆けつけて、実験室には人が溢れ返り、幽霊は来日したハリウッドスターみたいに取り囲まれています。
そして十分も過ぎた頃でしょうか、幽霊はパッと皆の前から消えてしまいました。
翌朝から研究所は大忙しです。幽霊に関するデータを分析して、幾つもの仮説が立てられ、昼夜を分かたぬ議論が沸き起こりました。
それは喧々囂々、口角泡を飛ばす凄まじいものでした。その結果、幽霊に関する議論は、いくつもの学派に分裂し、研究所内は大混乱に陥ってしまいました。
「幽霊は集団幻覚だ」「太陽黒点の影響だ」「コンピュータのバグによるデータエラーだ」「所長がお墓参りをサボったせいだ」などという明らかに迷走した論から、「観測者がいるから幽霊が観測されるのであって、この研究所を放棄して、全員が出ていけば幽霊は存在しない」という本末転倒なものまで、議論は収拾がつきませんでした。
数日を経て、学者たちが皆一様に精根を使い果たした頃、所長が意を決したように言いました。
「幽霊のことは、幽霊に聞いてみよう」
早速、徳の高いお坊さんが研究所に呼ばれました。シュレディンガー実験室の中に護摩壇が設えられて、護摩が赤々と焚かれました。
お坊さんが読経を始めます。その後ろに座る所長や学者たちも、こうべを垂れました。
すると待ちかねたように、勢いよく実験室のドアが開いて、幽霊が部屋の中に踊りこんできたのです。
皆は呆気にとられました。
幽霊は一同を見渡して、
「あの、喋っても、よろしいですか」
と遠慮がちに言いました。
「アタシは、この土地で三百年前に死んだ者でございます。名前はもう、すっかり忘れちまいました。大きな商家の三男坊だったんですが、色々とありまして、大層恨みを残して死にました。
死んで百年くらいは随分な暴れ方をいたしまして、一帯の村から、それは怖がられていたんです。
それが、ここ十年ばかしは、さすがに名前と同じで自分の恨みごともぼんやりして参りまして、そろそろあの世に昇っちまってもいいんじゃないか、と思っていたんです。
ところが、つい先日の事です。アタシが死んだ辺りに、一匹の仔猫がやって来ました。親とはぐれたのか、がりがりに痩せておりました。
アタシは生前から猫が大好きなもんで、こりゃあいけねえってんで、どっかの村人を呼んで来ようとしたんですが、生憎アタシが暴れたばっかりに、近所に村なんか一つも残って居やしません。
困った所で見つけましたのが、こちらの研究所なんでございます。
夜な夜な冷蔵庫から食べ物を失敬して、仔猫にやっておりました。
お陰様で仔猫は元気になったんですが、代わりに困った事が起こりました。
猫を助けて功徳を積んだせいですか、アタシの体がどんどんと、あの世に引っ張られるようになってしまったんです。
幽霊としての重さが足りなくなっちまったんですね。最近じゃあ、ちょっと気を抜くと、ふわーっと宙に浮いちまうんですよ。
しかし、このまま上に昇っちまったら、仔猫の世話をする者がおりません。それで、こちら様には何の恨みもないんですが、恥を忍んで、こうして化けて参りました次第です」
研究所の地上の出入り口付近を探してみますと、果たして一匹の仔猫が見つかりました。
幸い、研究員の中で猫好きの者が、仔猫を引き取って世話をする事になりました。
そのことを伝えますと、幽霊は大層よろこんで、研究所の皆に何度も頭を下げ、やがてすーっと、上の方に昇っていったのです。
以来、研究所での不思議な現象は、ピタリと止みました。
幽霊が昇天した時に、重力子が観測された事が切っ掛けで、学者たちは「量子重力」の研究も始めました。
それからひと月も経った頃でしょうか。
ある日、地下のいちばん奥の実験室、あのシュレディンガー実験室から、物凄い音が聞こえました。
学者たちが、再び実験室のドアを開けると、そこには、部屋に収まり切らない程の、巨大な一匹の猫がいたのです。
猫は、先がいくつにも分かれた尻尾を持ち、金色の眼はらんらんと光っています。そして、地鳴りのような音を立てて、喉を鳴らしていました。まるで化け猫です。
見ると、その化け猫の首からは、一枚の札がぶら下がっています。札には、まるで幽霊が書いたような、と申しますか、明らかに幽霊が書いたとしか思えないユラユラとした文字で、次の様に書かれていました。
「大変お世話になりました。お蔭様で安心して成仏できます。つきましては、皆さまへのお礼といたしまして、シュレディンガーの猫、というのを私が手懐けて連れて参りました。どうぞ、研究のお役に立ててください」
化け猫は、まるで切れかけた蛍光灯が明滅する様に、現れたり消えたりしていたのです。その姿は、存在するとも、存在しないとも、どちらとも言い難いものでした。
学者たちは驚き、そして、途方に暮れた目で化け猫を見ました。
その胸中を、知ってか知らでか、シュレディンガーの化け猫は、真っ赤な舌で自分の前脚の肉球を、ぺろりぺろりと美味そうに舐めていたのでした。




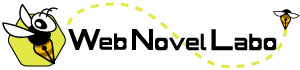

コメント