『叔父の帰郷』 作:彼方ひらく

こちらの作品は約1万字の、不思議なことは起こらない短編小説です。
まだ少女の頃に一人旅をしたのは、遠くアルゼンチンに住む叔父に会うためだった。
ちょうど私の両親が結婚した頃に地球の裏側に居を移したという叔父は、インターネットどころか電話もない辺鄙な場所に住んでいるらしく、年に一度「橋元夏樹」宛てで送られてくるクリスマスカードだけが便りだった。いつも同じプロペラ機の絵カード。擦れた青いボールペンの筆跡で、二、三行のぶっきらぼうなメッセージだけが記されている。なぜ実兄にあたる父宛てではなく、姪の私なのか、そのときは気にもしなかった。私は会ったこともない叔父の手紙になど興味はなく、年によって読むこともあれば読まないこともあったが、中学三年生の夏に半年遅れで初めての返事を出した。今年の冬休みに叔父さんに会いに行きます、と。
きっかけは一本のビデオテープだった。祖父母が早くに亡くなって鉄工所の経営を継いでいた父が、組合の慰安旅行で不在にした夜。自室のある二階から階段を降りると、居間から、ちらちらとテレビの灯りが漏れていた。陽気な笑い声が聞こえてくる。 髪を下ろした母が珍しく缶のお酒を片手に、ビデオのリモコンを操作していた。テレビ画面には驚くほど若い父と、父に似た青年が向かい合う形で映っていた。二人はテーブルに肘を立てて、うなり声を上げながら腕相撲で闘っている。
映像の中の父は今と同じ溶接焼けした顔で、ぴったりとしたLサイズのティーシャツでは隠しきれない逞しい身体つきをしていたが、意外にも力強く握り込んでくる青年に押し切られて勝負がついてしまった。父は腕をテーブルの上に寝かせたまま、呆然としている。
「見て、このお父さんの顔」
母は口もとに手を当てて愉快そうに笑うのだが、父の表情はやがて、真っ赤に燃え上がり、眉がうねり唇がめくれ上がるような、とてつもないものに変化した。男の人というのは腕相撲で負けたくらいで、こんな顔をするものなのだろうか。私は気圧された。
「‥‥こっちの人、もしかして叔父さん?」
「そうそう、礼ちゃんよ。夏樹が生まれたときにね、一度だけ日本に帰ってきたの。これは私が撮ってるの」
母はまた笑って、ビデオを巻き戻した。 まだ余裕の父が、嬉々として叔父らしき人に人差し指を突きつけている。
「お前から言い出したんだ、後悔するなよ。このビデオが証拠だからな。お前が負けたら日本に戻って、我がハシモト鉄工所の専務だ」
画面の外から母の声がする。
「そんなこと言ってあなた。礼ちゃんが勝ったら?」
「礼二が? そんなことがあるか」
レスリングでインターハイ出場経験を誇る父は自信満々で、挑発的に笑う。ジャケットを脱いだ叔父は黙ってシャツの袖をまくる。露わになったのは父に勝るとも劣らない、真っ黒に日焼けした隆々たる二の腕。画面が少し動揺した。父も口をあんぐりと開けた。
「約束するよ。でも俺が勝ったら、兄貴となっちゃんの子供の名前を付けさせてもらう」
母によれば、学生時代どちらかと言えば細身だった叔父の腕は、日本を出る以前より二回りは太くなっていたという。
叔父は母の夏子から一文字とって、私に夏樹という名前を付けてくれた。
私が叔父さんに会いに行きたいと相談すると、何日も鉄工所を留守にできないと父に一蹴された。私は一人でも行きたいと粘りに粘った。父は治安がどうとか、アルゼンチンの経済は破綻しているとか難しいことを言って猛反対だったが、母の一言「自分の娘を信じられない人だとは思いませんでした」が利いたらしく、二つの条件付きでようやく許可が出た。一つは年内に高校進学を推薦で決めること、もう一つは旅費を自分で工面すること。
私は一心不乱に勉強して無事に推薦入試に合格を果たし、一度も使ったことのなかったお年玉貯金を全額引き出して備えた。
正午に成田空港で旅客機に乗り込んで十二時間。地球の回転を追い抜いてアメリカのヒューストンに着くと、ターミナルのガラス越しに差し込んでくる光はまばゆくて、時刻は出たときとほとんど変わっていなかった。時差って本当にあるんだなあと感慨深くトランジットを過ごし、夕方に再出発。機内で眠っている間にエセイサ国際空港に着いていた。
日本から持ってきたダッフルコートはものすごく邪魔になった。南半球は日本と季節が真逆で、十二月の下旬は夏なのだ。カウンターゲートのベルトコンベアーから流れてきた自分のスーツケースを受け取って、待ち合わせ場所に向かうと、長いエスカレーターの上から、東洋人らしい男性が一人立っているのが見えた。ミラーシェードのサングラスをかけて、暑いのに昔の映画で見たようなチョコレート色のフライトジャケットを着ている。私は自分が入れそうなくらい大きなスーツケースを引っ張るのが難しくて、ケースを前にして押しながら駆け寄った。
「あの、橋元礼二さんですか?」
「そうだよ。君は、なっちゃんか?」
耳に新鮮な響きだった。母の名前が夏子で、親戚が母のことをなっちゃんと呼ぶので、私はいつもただ夏樹と呼ばれたからだ。
「はい、そうです! 夏樹です! あの、初めまして」
「君がまだ生まれたばかりのときに一度会ったことがあるよ」
「あ、そうですか。あの、日本からいっぱいお土産を持ってきました」
叔父さんはすこし目線を動かしたのか、「そう。じゃあ行こうか」とだけ呟くと、私に背を向けてポケットに手を入れたまま歩き出した。私は慌ててコートを抱え直し、スーツケースを押してつんのめりながら追いかけた。
クリスマスカードとビデオの中でしか知らなかった叔父さんが、どんどん私の中でリアルになってくる。ターミナルを出て玄関口の背の高い自動ドアを抜けると、熱風が全身に吹きつける。叔父さんを見失わないよう、強烈な日差しを浴びながら汗だくで歩いていると、沿道に駐車しているトラックに背中を預けていた白人の女の人が、手を振って私たちの方に近づいてきた。濃い青紫のタンクトップにデニムのホットパンツ。長い手足。癖のある長い栗毛が絡まり合って、少し灼けた肌にかかっている。英語が喋れない私が緊張していると、女性は突然ぺこりと頭を下げた。
「アマラとモウします。私のおじいさんは、日本人です」
丁寧な日本語だったけど、雰囲気で気さくな人だと分かった。私が挨拶して「ハーフなんですね」と言ったら、「クォーターだよ」と叔父さんに訂正された。
三人一列で乗り込んで、アマラさんの運転でトラックはごとごと走り出した。なんとなく叔父さんには話しかけづらかったので、よく喋ってくれる他人のアマラさんがいて、私は正直ほっとしていた。
「ナツキ、フィエスタ行く?」
「フィエスタ?」
「今年サイゴの日。パーティー」
きっと年越しパーティーだ。私は叔父さんの顔を見た。
「行きたいなら行くといい」
「レイジも行く」
「俺は行かない」
アマラさんはマンガみたいにほっぺたをぷーっと膨らませてむくれた。
途中に寄ったスーパーマーケットでは、日本と違って商品は何もかも量が多くて、ジャガイモの袋は抱えるくらいある。ポップや商品ラベルを見て、私はようやくアルゼンチンで使われている言葉が英語ではなくスペイン語だということを知った。
叔父さんは似たような豆の缶をどんどんカートに放り込んでいく。
「え、そんなに買うの? 食べきれないよ」
「半月分だよ」
叔父さんの家は一体どんな所にあるのだろう。再び走り出したトラックは小麦畑を割って真っ直ぐに伸びた道を一度も曲がることがなく、叔父さんは無口で、小一時間もするとアマラさんとの話も尽きてしまった。
時差ぼけしていた私は眠り込んでいたらしい。トラックがブレーキをかけた衝撃で目覚めたとき、窓から塔が視界に入った。あれは管制塔だ。短い滑走路が一つきりの、エセイサ国際空港のミニチュア版のような小さな飛行場に着いていた。格納庫の日陰の中で、つなぎの作業服を来た白人の大人があちこちで作業をしている。アマラさんから、彼女のお父さんの会社があるアスール・デ・シエロ飛行場だと教えてもらった。
滑走路の手前には小さな飛行機が間隔をつめて並んでいて、一機のセスナに、私はクリスマスカードのイラストを鮮明に思い出した。スカイブルーの機体に白抜きでLQ―777と書かれた翼は太陽の光を照り返して美しい。
「それはレイジのヒコウキ」
アマラさんが指差す。叔父さんがセスナを持っているなんて、うちの家族は誰も知らないはずだ。叔父さんはゆっくりとセスナの周りを歩いて何かを点検すると、車輪止めを持ち上げて、扉を開き、機内に放り込んだ。
「なっちゃんは右だ。シートベルトをしろ」
鼻先をつんと上げて斜めに空を見るセスナは二人乗りで、思いのほか柔らかな座席に着けば、私の身長では計器とプロペラの先端しか見えはしない。叔父さんは買い物を座席の隙間に詰め始めた。足元にあった消火器が埋もれかけている。最後に私はジャガイモの袋を持たされた。
「叔父さん、運転できるの?」
「ああ」
叔父さんが運転席についてエンジンをかけると、機体全体がぶるぶる震え出す。高速で回転を始めたプロペラは残像だけになった。左右を確認しながら、手を振っているアマラさんをちらりと見て、叔父さんは右手に無線を持って管制塔と英語を話しつつ、左手で操縦桿を握ってセスナは進み始めた。車のように滑走路を走ってカーブから長い直線に入る。ぐんぐん加速する。プロペラの音が高くなり、残像さえ消えた。
機首の下がったセスナが水平になって、正面の窓から地平線が上ってきた後で、自分がとっくに空の中にいるのだと気づいた。右手の窓を覗くと、翼の下に緑の壮大なパッチワークが果てしなく広がり、飛行場はあっという間に埋もれて見えなくなってしまった。
私の乗ったセスナの嘘みたいにペラペラした影が、波打ちながら青い草原を、小麦畑を、民家の屋根を泳いでいく。私はその遙か上空の、深い青の中にいる。こんなに気持ちいいことは他にない。嬉しくて堪らなくなり、できるなら座席で飛び跳ねたかった。
「ねえ、叔父さん。宙返りしてよ!」
「こいつのエンジンじゃ無理だな。それに機体の強度がもたない。バラバラになるよ」
「じゃあさあ、じゃあさあ、今からナスカの地上絵、観に行こうよ!」
「ナスカか。国境を二つ越えるんだ。軽飛行機で行く距離じゃないかな」
真っ直ぐ前を向いたままの回答。叔父さんがこんなにちゃんとしているのは意外だった。父はいつも叔父さんを悪く言っていたからだ。どこにも居場所のない風来坊とか、どうせもう地球の裏側で野垂れ死にしてるとか、橋元家の裏切り者だとか散々だった。
涼やかな風が窓から吹き込む。アルゼンチンは夏なのにちっともじめじめしていなくて、混じりけのない澄んだ空気でどこまでもどこまでも見晴らすことができる。私は懸命に目をこらし、西の空に地図帳で覚えたアンデス山脈を探した。
「日本の空と全然ちがうね」
「どこだって同じさ。空は世界に一つなんだ」
折角良い気分なのに、叔父さんが話を合わせてくれないのがもどかしかった。
地平線から湧き起こった入道雲へ飛び込むみたいにセスナは飛翔を続けた。点のような牧牛と荷車のある低い丘を越えて、少しずつ木々が目立ち始め、林が見えてきたころ、大地に途切れた灰色の道を見付けた。それは滑走路で、そばには木の陰に半ば覆われた小屋が一軒ひっそりと建っている。
機体が傾いてセスナが旋回を始め、高度が下がってきたので、叔父さんの家に着いたのだと分かった。時間にすればほんの十数分だ。
叔父さんが家のドアノブに手をかけると、黒ずんだ木の戸はそのまま開いた。
「鍵、かけなかったの?」
「そんなものないよ」
家の中はいつかテレビドラマで見た山小屋のようで、板張りの床に木肌をさらしたテーブルと作り付けの棚、それから椅子が二脚。一脚は古くて、使い込まれていた。もう一脚は一回り小さく、背もたれの腰がくびれていて、色は真っ白ですごく清潔な感じがした。
「もしかしてこの椅子、私のために買ってきてくれたの?」
「いや」
叔父さんは短く否定したけど、明らかに白い椅子だけが他の家具から浮いていたので、私は勝手に座った。わりと高級なのか、クッションがなくても座面がおしりの形にへこんでいるのでとても座り心地が良い。
居間の奥の扉を開くと、工具のある鉄の棚やドラム缶が並んだ格納庫で、住居部分は居間と物置を改造した狭い寝室しかなかった。
一日も過ごすとショックなことが沢山あった。テレビもエアコンもないし、あちこちに虫がいる。電気はガソリンを入れた発電機で作らなければならないし、ガスはボンベで、水道がないから水は井戸からくみ出すか、数キロ離れた民家でポリタンクに入れてもらうしかなかった。洗濯は石けんを使って手で揉み洗いして、セスナと格納庫の間に紐を張って干す。無人島に来てしまったんだと思った。
周りには何もないし、誰も来ないし、毎日やることは特になくて退屈で仕方なかった。日本から持ってきた冬休みの宿題のドリルは一日で終わってしまった。叔父さんの本棚に収まっている大量の小説は全て日本のもので、中には去年のベストセラーもあったけど、どれもスペイン語や英語で、私には読めない。
そんな毎日だから、叔父さんが飛行機で仕事に出かけるときには必ず着いていった。叔父さんは農家の足の不自由なお婆さんに頼まれて空から肥料や農薬を撒いたりもするし、飛行場から観光客を乗せて遊覧飛行へ飛び立ったりした。週末は半袖の制服を着て、見習いのパイロットを養成する教官にもなった。
アルゼンチンに来て二週間弱、待ちに待ったアスール・デ・シエロ飛行場の年越しパーティーの日、私はバンザイして出かけた。
スペイン語がしゃべれない私に、みんな本当に親切で優しくて、嬉しかった。その日は駐車場が車でぎゅうぎゅう。昼間から飛行場の職員の奥さんや子供たちも来ていたし、ブエノスアイレスなどの都会に出ていた人たちも里帰りしていたらしかった。
沢山の家族を見て、叔父さんはどうしてこの国で結婚しないのだろうと思った。それともそろそろ、日本に帰るのだろうか。
買い物から帰ってきたアマラさんが言った。
「レイジはイッショウ帰らない」
一生、帰らない。
「アルゼンチンにホネを折る」
「‥‥うずめる?」
「アハ! デスデ・ルエゴ。そう。ホネをウースメル!」
「でも叔父さんは日本人なんだよ」
「いいです。私のお父さんとお母さん、スペイン人。アルゼンチンはイミンの国」
日が暮れて窓から差し込む光が弱まり、誰かが照明のスイッチを入れた。広い部屋の真ん中に置かれた大きな長方形のテーブルにはカラフルなモザイク柄のテーブルクロスが敷かれ、赤くてつやつやしたテーブルランナーが端から端へ垂らされた。銀色の食器と料理と、花瓶と蝋燭台で埋め尽くされる。
全員が席につくと、急に静かになった。みんな両手を組んで目を閉じ、神様にお祈りを捧げるので私も真似る。
それから大人は赤いワインで、子供は黄色いコーラを手に持つ。アマラさんのお父さんがスペイン語で声を上げると、みんなが繰り返して唱和した。
「ア、ドン・ルエイシ、イ、ナツキ!」
乾杯する全員の顔が私の方を向いていた。
串を通した肉の塊はスパイスの不思議な香りがして、大皿に盛られたパイの断面には詰め込まれた干しブドウと挽肉が見える。鍋の黄色いシチューには色んな種類の豆と肉、それからお米もいっぱい入っていた。
日本からやってきた私には大きな部屋の中心に席を用意され、もてなされた。アルゼンチンの法律では未成年が一人で海外に出るのは難しいから、偉大なことだというのだ。まるで芸能人みたいな扱いで、私はついついにやけてしまった。
お腹いっぱいになった頃、照明が一度消えた。停電かなと思っていると、また灯りがつき、階段の上に立っているのはアマラさん。肩を出した大胆な赤紫のドレスに着替えていて、黒いスーツ姿のお父さんにエスコートされて降りてきた。みんながさっと退いて空間を作る。いつの間にか背後にはアコーディオンやバイオリンを構えたおじさんたちがいて、蛇腹を開くのを合図に、メロディーに乗って二人は踊り出す。くるくると入れ替わる男女、情熱的なドレープの裾から飛び出した長い脚が絡み合うステップ、しなやかに反る上半身のボディーライン。音楽が鳴り止んでポーズが決まると、私は夢中になって拍手した。
そのとき、片手でカーテンを開いて夜空を見ていた男の子が叫んだ。
「グアーウ! ドン・ルエイシ!」
途端にみんなが色めき立って、子供たちは我先に外へ駆け出す。私も外に出ると、滑走路の直線を示すように路面の埋め込み式ライトが光の道を作っていた。
大きな満月を背に、かすかな明かりを灯した飛行機が迷いもなく降下してくる。闇に浮かび上がったのは蒼褪めた機体。セスナから降りてきた叔父さんを、あっという間に大勢が取り囲んだ。大人の男の人たちが入れ替わり立ち替わり、にかっと笑っては、降りてきた叔父さんと拳を突き合わせていく。女の人たちは、叔父さんに抱きついて、右と左の頬にキスをする。大人も子供も口々に言う言葉は「ドン・ルエイシ」。私を迎えに来ただけなのに随分大げさだと思った。
「アマラさん、ドン・ルエイシってなに?」
「レイジ。スペイン語は、レイジはルエイシ。ソンケイするから、ドン・ルエイシ」
私は目が覚めた気がして、ぎゅっと両拳を握った。私が日本から来た勇敢な少女だからでも、アルゼンチンの人たちが陽気だからでもない。私は叔父さんの姪だから、みんなに受け入れられたのだ。そのくせ、私は自分の叔父さんのことをよく知りもしないのだ。
「あの、アマラさん礼二と付き合ってるの?」
首を傾げて「ツキアウ? 恋人?」と言うので私が頷くと、壊れたピアノの蓋が開いたみたいに大声で笑い出した。
「私のお父さん同じネンレイ」
「叔父さんが? アマラさんは何才なの?」
「ジュウナナ」
まさか。私と二つしか違わない。
「そしてレイジは好きなオンナいる」
「え、誰?」
「知らない」
それで叔父さんは日本に帰らないのだろうか。興奮した私が質問攻めにしていると、アマラさんは一つ昔の出来事を話してくれた。
小さな街に大雨が続いた夜、まだ一才にもならない赤ちゃんが高熱を出した。この国のほとんどの街がそうであるように、起伏のない平野の住居地は道路があちこち水没してしまい、車が使えない。しかも、悪いことに街に一つしかない病院の医師は不在にしている。
アスール・デ・シエロ飛行場から飛行機を飛ばす話が出たが、雨で視界が悪くて当時の社長は墜落を恐れてフライトを全面的に禁止した。意識を失った瀕死の子供を飛行場まで抱えてやってきた母親は、しがみついて訴えたが、社長も断腸の思いだったという。飛行場の男たちは皆、歯を食いしばった。
そこへ臨時に雇っていた一人のパイロットが名乗り出た。無口な男で、飛行場に来てから二週間も経つのに、中国人だと思われていたし、スペイン語が話せないのではないかという噂さえあった。その男は自分をクビにしてくれて構わない、自分は飛行場には関係のない人間で、勝手にセスナを飛ばすと言った。
「レイジ、行くと言わないがよかった。ヒコウキが落ちる、自分死にます。赤ちゃんがビョウキ死ぬ、そしてレイジのセキニンだからです」
宙返りをしない叔父さんが、そのとき、どんな気持ちで飛んだのだろう。
「レイジときどき赤ちゃんに日本語教えた」
アマラさんはにこっと笑って、「赤ちゃんはワタシ」と言った。
帰りの夜間飛行で私が口を開かなかったので、珍しく叔父さんの方から「何かあったのか」と話しかけてきた。
「叔父さんは日本が寂しくないの?」
「いや」
「私はもうすっごい寂しいよ。みんな家族がいるんだもん。日本に帰りたいよ‥‥」
「後、数日じゃないか」
「‥‥ねえ、叔父さんの好きな人がアルゼンチンにいるって本当?」
「誰から聞いたんだ?」
「アマラさんだよ。ねえ、好きな人いるの?」
叔父さんは少し間を空けて答えた。
「いないよ」
「じゃあなんで帰らないの?」
「なっちゃんが大人になったら分かるよ」
私がまた黙りこむと、叔父さんが口を開く。
「好きな子には随分昔にフラれたんだ。そういう忘れたいことってあるだろう。思い出しちまったら、空に身を投げ出すに限る」
なんだか可笑しかった。
「フラれたからずっと飛行機に乗ってるの?」
叔父さんの横顔が月影の中で笑った。初めて見る表情は、父にすこし似ている気がした。
叔父さんの家にはカレンダーもないし、毎日暑いので全然実感がなかったけど、間違いなく年が明けて数日が経っているはずだった。豆ばかり食べる毎日にも別れを告げて、私はスーツケースを開き、埃まみれになったダッフルコートをはたいて帰国の準備をしていた。叔父さんはちっとも寂しがってくれなかったから、私はどうしても意地悪を言いたくなった。
「‥‥もしかして私が来たの迷惑だった?」
「いや」
色のない言葉。私は立ち上がり、もう使い道のなくなってしまった白い椅子を戻した。
「うそ。ごめんなさい。椅子、買ってくれてありがとう」
叔父さんは胸ポケットからサングラスを取り出して、身につけてから言った。
「買ったんじゃない。作ったんだ」
「‥‥え、叔父さんが?」
「他に誰がいるんだ?」
私が呆然としていたからか、叔父さんはゆっくりと説明するように言葉を足してくれた。扉を開き、北の林を指さす。
「あそこから斧で伐り出したんだ。三ヶ月ほど乾燥させて、図面を引いて、ノコで切り出してカンナをかけて、ほぞを噛ませた」
私は何も言えなかった。
「やすりは四十番から始めて、千番までだ。ヤニ止めとペンキを塗って、ニスも塗った。背もたれを張って、半年はかからなかった」
私の居ないこの家で、叔父さんがひとりぼっちで、薄暗い部屋の中で、風の音を聞きながら椅子を作り続けている長い長い時間を私は想像した。私が帰れば叔父さんはまた独りになる。上手く言葉にできない感情が胸の中で渦を巻き始めていた。
「叔父さん、私と一緒に日本に帰ろう」
「俺は帰れない」
いつもそうやって答えを用意している。
「なんで? ちゃんと言葉にして言ってくれなきゃ分かんないよ!」
私はお腹から叫んで、自分が大声を出していることに気づいて何回も瞬いていた。叔父さんは、私の頭に手のひらを乗せて言った。
「大人になれば分かるさ」
地球半周のフライトを終えて旅客機を降りると、空港につながる搭乗橋の床が冷え切っているのが、靴底から嫌というほど伝わってくる。帰国したら家に電話をかけるように言われていたけど、送ってくれたときに別れた国際便発着場のベンチに、車の免許を持っていない母がわざわざ迎えに来てくれていた。
駅までのリムジンバスの中、窓の外にちらつく雪を見て、ああ、もう日本に帰ってきてしまったんだと思った。そこでやっと私は、向こうに滞在中に最低でも三日に一度は日本に電話するという父との約束を思い出した。
「お父さん怒ってる?」
「そりゃあね。でも、さみしそうよ。それより礼ちゃんは元気にしてた? 相変わらず?」
今の叔父さんしか知らない私には答えにくい質問だった。きっと叔父さんは相変わらずなのだろう。十数年もの間、ずっと相変わらずなのだ。
「さみしそうだった」
「‥‥そう。私たちだって、おかえりって言いたいわよね」
私は帰国数日で窮屈な日常に馴染んだ。そして、二度とアルゼンチンに渡航することはなかった。誰もが叔父のようになれはしない。
あのとき叔父のことを笑った私は、一人の人間を変わらずに愛し続けることがどれほど難しいか、じきに思い知った。短大時代に一度、社会人になってから一度、男性と付き合ったこともあったが、私は本当にこの人のことが好きなのだろうか、これは本当の恋なのだろうかと、余計なことばかり考えて、どちらもあまり進展しないまま終わってしまった。
叔父のせいだ。そして私のせいでもある。あの夜間飛行で、叔父から聞いた言葉が、あの一瞬の切なげな眼差し、月光が陰影を浮き彫りにした横顔が、私の心に魔術のように写し込まれてしまったのだ。年を取るにつれて次第に濃くなるその魔力に打ち克つ術がない。
二十八枚目のクリスマスカードが届いた翌年の晩春、例年の会社の健康診断で母に乳がんが見つかった。既に肺にも転移しているような状態だった。私は会社を辞めて独り暮らしのアパートを引き払い、実家に戻って母の担当していた鉄工所の経理を引き継いだ。
叔父に母のことを報せようとすると父は烈火の如く怒り、もし連絡を取れば勘当するとまで宣告されては、母の心労を考えると諦める他はなかった。母は梅雨明けを待っていたかのように容態が急変し、五十四才の若さであっけなくこの世を去った。
私は通夜の準備中に、大学で学んだスペイン語を思い出しながら、インターネットでアスール・デ・シエロ飛行場の電話番号を調べ、密かに国際電話をかけて叔父への伝言を頼んだ。私も父も時間をかけてこの不幸を受け入れる準備をしたが、叔父にとっては青天の霹靂になる。しかし私には伝える義務があった。
友引をはさんで告別式は三日後に行われた。頭を垂らして読経を聞く黒服の群れ。最後の一人が焼香を終えたとき、ざわめきに振り返ると、あのチョコレート色のフライトジャケットを着た叔父が真っ直ぐに歩んできて、最後部の空席に腰を下ろした。隣に座っていた父は決して振り返らない。遺影の母は笑顔のまま。
十人ほどの親族と共に葬儀会社のシャトルバスで丘の斎場に向かう間、幾人かが叔父に話しかけた。臆病な私は父の目が気になって、叔父の側に寄ることもできない。
火葬場へ棺を運び込んだ後、控え室から叔父が外へ出たのを見計らい、少し時間を空けて私も外へ出た。白亜のほっそりとした煙突から美しい煙が立ち上り、たなびいていた。
想い人はアルゼンチンにはいないと叔父は言った。だからこそ、叔父は帰ってこられなかったのに。私は駆け寄った。
「叔父さん!」
回り込んで正面に立った瞬間、両肩がずっしりと重くなるのを感じた。叔父が摑んだからだ。叔父は下を向いて、嗚咽していた。私だって、痛みで身体がばらばらになってしまいそうだった。指先から伝わる震え。アスファルトを濡らし、黒い染みを穿ち続ける滴。
「なっちゃん‥‥」
そして叔父は幼い子供のように全身を振り絞る鳴き声をあげた。それは斎場いっぱいに、割れんばかりに響き渡った。喫煙所にいた親族が振り返ったのが気配で分かったが、声をかけてはこなかった。
「おかえりなさい」
私は抱きよせて、肩越しに小さく声をかけた。見上げた私の視界いっぱいに、叔父さんの愛した青空が広がっていた。




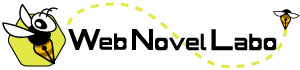
コメント