『水面下の出来事』 作:佐久村志央

『水面下の出来事』
──ねえもう聞いた? 恋の願いを叶えるおまじない。
──聞いた! 毎朝誰よりも早く登校して、校庭の池に願い事するっていうやつ。
──でも一回だけじゃダメなんだよ。月曜から金曜まで毎日、一番乗りじゃないとやり直しになるの。
──ええっ、私いつかやってみようと思ってたんだけど、早起き苦手だから一週間ずっとは無理だよお。
──その人が願いを叶えるのに相応しい人間かどうか、一週間かけて見極めるんだって。
──見極めるって、誰が?
──それは……池の神様、とか?
リクはさっき教室で立ち聞きした女子達の噂話を頭の中で反芻しながら、通学路をひとり走っていた。金曜日なのに体操服を教室に忘れたのを帰り道の途中で思い出し、学校まで取りに戻らなきゃいけなくなったときはガックリしたけど、逆にそれがラッキーだった。
「一週間っ、毎朝っ、校庭の池に一番にお祈りっ!」
忘れないように、走りながら口の中で何度も唱える。
普段のリクなら、おまじないだの占いだの、そんな女子が集まってキャッキャするような話題に興味は示さなかっただろう。けれど、今回ばかりは聞き流せない理由があった。
三学期が終わったら、クラス替えがある。四月に五年生になったら──
「……花野さんと、クラスが離れちゃうかもしれない」
嫌な想像はよそう。リクはぶるぶると頭を振って、来週からの作戦を練ることにした。
花野さんは、四年生で初めてリクと同じクラスになった。
正直、最初はあんまり気に留めてはいなかった。言っちゃあ悪いけど花野さんは特別美人というわけでもないし、運動が得意とか、勉強がめちゃくちゃできるとか、逆に何かがすごく苦手とかそういうクラスで目立つような要素が本当になにもない女の子だったからだ。
だけどある日、リクが放課後グラウンドでサッカーをしようと友人達と連れ立って校舎を出たとき、花野さんが変わった場所に居るのを見つけた。
サッカーコートまで一直線だった足をふと止めてそっちに近づいてみたのは、ちょっとした気まぐれだった。
「何してんの?」
「ウサギの気持ちになってるの」
「ウサギの気持ち?」
「そう」
花野さんは、校舎の外にあるウサギ小屋の前でたったひとりでしゃがみ込んで、ウサギがヒクヒクと鼻を動かしながら野菜を齧っている様子を眺めているのだった。
ちらりと見えた横顔に、とても真剣な眼差しが覗いていた。白いふわふわの毛の一本一本の動きすら見逃すまいとするように。
「私、こないだ飼育係になったでしょ。ずっとやりたいと思ってた係だったから、先生に聞いたの。『どうやったら良い飼育係になれますか』って」
「えらいなあ」
素直に感嘆の声が漏れる。
リクなんて、いかに係の仕事や掃除当番から逃げるかばかり考えているのに。
「それでね、先生は『世話をする生き物の気持ちになってどうやったら嬉しいか考えるといいよ』って言ってたの。だから、ウサギの気持ちになりに来た」
花野さんはそう言うと、またじっとウサギを見つめ始めた。なんとなくリクもその横にしゃがみ、並んで飼育小屋の中を眺めてみる。
ウサギはこちらを気にするでもなく、せっせとニンジンを食べ進めている。
「こうやって見てても、おれにはウサギの気持ちなんてぜーんぜん分かんないや」
「えっ」
驚いたように振り向いた花野さんに向かって、リクはぺろりと舌を出した。
「おれ、ニンジン嫌いだもん」
花野さんは呆気にとられたように一瞬固まって、すぐにぷっと吹き出したのでリクもつられて笑った。
花野さんってすごく良い子だな、とリクは思った。きっと先生は飼育係の心構えとか、考え方の方向性を示す意味で「生き物の気持ちになる」って言ったのだと思う。
けれど、花野さんはそれをまっすぐに受け取って、本気でウサギの気持ちになろうと頑張っているのだ。
「ウサギの気持ち、分かりそう?」
「うーん」
花野さんは首をかしげた。
「よく分からないけど、ちょっとニンジンは食べたくなってきたかも」
花野さんがそう言った瞬間、ずっとそこにいたウサギがニンジンを咥えたままぴょんと巣穴に飛びこんだ。まるでずっと人間の話を聞いていて、大事な食事を奪われると考えたかのようだった。その様子が可笑しくて、リクは花野さんと顔を見合わせてまた笑った。
その日からだ。リクはその日から、花野さんのことが気になって仕方がなくなってしまった。
ありていに言えば、恋に落ちたのだ。ウサギが巣穴に飛び込むような速度で。
月曜の朝、いよいよ作戦開始の日。誰よりも早く学校に行って、池の神様にお祈りするのだ。
リクの母さんは珍しく自分から早起きして支度を始めた息子を見て、熱でもあるのかと思ったらしい。何度もリクのおでこに手を当てて、首をひねっていた。
登校すると、狙い通り学校にはまだ誰もいなかった。校庭を端までダッシュで走り抜け、池の前にやってきたリクはそこではたと足を止めた。
お祈りって、何をすればいいんだろう?
神様にお祈りすると聞いてイメージできるのは、お正月に家族で出かける初詣くらいしかない。なんとなくその時の記憶を頼りに、池に手を合わせて頭の中で
(花野さんとの恋を叶えてください)
と念じてみる。顔を上げると、池の中を何匹かの鯉が泳いでいるのが見えた。
「この池、魚も住んでたんだ……あっ!」
水面をのぞき込んだリクの正面を、ひときわ鮮やかな朱色をした鯉が通り過ぎた。その背に大きなハートマーク模様を見つけたのだ。

きっとあれが女子達の言っていた池の神様だ!
そう直感してリクはもう一度勢いよく手を合わせてから、誰かに見つかる前に教室へ向かった。
その翌日も、その次の日の水曜も、リクはちゃんと朝一番にお祈りに来た。ハート模様の鯉に手を合わせ、祈る。小さく願いを口に出してみたりもした。
だけど、まだ花野さんとの距離が近づいているような実感はない。
やっぱり、池の神様なんてただの噂に過ぎないのだろうか。
「ねえ、ちゃんと効果出てんの?」
池に向かって尋ねてみても、当然返事はない。
ハート模様の神様を含む池の鯉たちはリクの方には見向きもせずに、池の中央付近で頭を寄せ合っている。なんだか話でもしてるみたいだった。
何を話しているんだろう。この人間が願いを叶えるに相応しいか相談でもしているんだろうか。
だったら自分は、相応しいと認められるだけの人間だろうか?
「……なんてね」
一瞬とはいえ、神様に気に入られようなんてことを本気で考えてしまった自分にリクは苦笑して、この日のお祈りは切り上げることにした。
木曜日、リクは大きな決意と共に池を訪れた。
「池の神様お願いします! 告白が上手くいきますように!」
気がついたのだ。恋の行方を神頼みにするべきじゃない。神様に願いを聞いてもらえるかどうか、ウジウジと悩んでいる時間があるならその時間で行動を起こせばいいのだ。
リクの手には小さな包みが握られている。その中には、ビーズで作ったブレスレットと一通の手紙。
昨日の夜、家族が眠ったのを見計らって書いたものだった。ラブレターなんておしゃれな仕上がりではないが、今のリクの精一杯の気持ちを書いた。
ブレスレットの方は、学校の宿題だということにして三歳上の姉に頼み込んで材料を分けてもらい、それはそれは厳しい指導を受けながら作った。
今日、この贈り物と一緒に、花野さんに直接気持ちを伝えるのだ。
「予行練習とかしとくべきか? えっと、オレは前から花野さんの事が好きで……いや、花野さんの笑顔がみたくて……なんか変かな」
花野さんはこれを聞いてどんな表情をするだろう。嬉しく思ってくれるのか、拒絶されてしまうのか……もしかしたら、困ったようにただ微笑むのかもしれない。
いざその瞬間のことを想像すると、なんだかとても無謀なことをやろうとしているような気になってきた。
「告白ってこんな怖いのか?! うおーやっぱり無理かも!」
リクがそう叫んで頭を抱えた瞬間だった。
ぽちゃん。
「えっ?」
綺麗にラッピングした手紙入りプレゼントが、振り上げた勢いでリクの手から離れて水面に飲み込まれていった。
「ああーーっ!」
池のフチに縋りついても手が届くはずもなく、もうリクのプレゼントは鯉たちに見守られながらゆっくりと池の底に沈んでいき、暗い水の膜に覆われていつしか見えなくなった。
その日、リクはろくに授業に集中できないまま一日中、池の底に消えたプレゼントについて考えることになった。
なにせラブレターとプレゼントを落としたなんて、先生にはとても言えない。放課後、生徒がみんな帰ったあとにどうにかしようかとも思ったけれど、運悪く木曜は塾があるからあまり遅くまで学校に残っていられない。
かと言って、自分がいない間に知らない誰かに拾われたりしたら──
「恥ずかし過ぎる……!」
残された選択肢はひとつだ。
明日の朝、誰よりも早く登校して、どうにかして池から回収しよう。先生の話を上の空で聞きながら、リクは覚悟を決めてひとり頷いたのだった。
金曜の朝、校庭の端に到着したリクの装備は万端だった。
池の底を掻き回すために持ってきた竹箒に、プレゼントを見つけたらすぐにすくい上げるための虫取り網。きっと泥とかで汚れているだろうから、それを入れるためのビニール袋などなど。
ほとんどのものは家の物置から勝手に拝借してきたものなので、家族に見つかるまでに返しておかなければならない。
「すぐに見つかるといいけど……」
そう呟いて、リクが池をのぞき込んだ時だった。
「もしかして、これ探してる?」
背後からよく知る声が突然聞こえて、リクは驚きのあまり池に落ちそうになった。
「うわっ! え、花野さん?!」
「わ、ごめんね! 驚かせるつもりはなかったの。あのね、これ、探してるんだよね?」
そう言って花野さんが差し出したのは、紛れもなくリクが回収しようとしていたプレゼントだ。なぜかその見た目は池に一度落ちたとは思えないほど綺麗なままだった。
どうして、と疑問に思うのを通り越して、狐につままれたような気分になる。
「どうして花野さんのところに?」
「ほら、私、飼育係でしょ。昨日は鯉の餌やりの当番だったから、放課後にここに来たの。そうしたら、池の外側の岩の上にこれがそっと置かれてて……」
花野さんはそう言って包みに視線を落とした。つられて花野さんの手元に目をやったリクは重大なことに気がついた。
封筒に入れていた手紙が開封されている。
「その手紙……!」
「ごめんね、持ち主が分かるかなと思って覗いちゃったの。そしたら宛名に私の名前があって、それで――」
花野さんは申し訳なさそうに、けれどどこかに高揚を隠し持った微笑みを浮かべて、言葉を続けた。
「読んじゃった」
「よ、読んだの?」
あの、夜中に一気に書いた、思いの丈をありったけ詰め込んだリクのラブレターを、花野さんが……
「うん、読んだ」
花野さんは、にっこりと笑った。
言うべき言葉が思いつかず、池を泳ぐ鯉のようにパクパクと口を開いたり閉じたりさせているリクの心境を知ってか知らずか、花野さんは手紙をとても大事そうにゆっくりと撫でた。
「手紙で気持ちを伝えてもらうのって、こんなに嬉しいことなんだね。私もお返事の手紙、書いてくるね」
「へ、返事……?」
「うん。『これからよろしくお願いします』って」
そうやって恥ずかしそうに頬に当てた右手には、リクが作ったウサギ模様のブレスレットが光っていたのだった。
その放課後、リクはポケットを膨らませてひとり池の前に立っていた。
「最初はただの噂かもって思ってたけど……」
池の神様の話は本当だったのだ。一度は諦めたはずの手紙がちゃんと花野さんに届いていたのだから。
リクはポケットの中から、隠し持っていた給食のパンを取り出す。今日の給食は大好きなきなこパン。このためにこっそり残しておいた。
そりゃあ本音は自分で食べたいけど、神様へのお礼にするならこれくらいするのが相応しいと思ったのだ。
リクは大きく息を吸って、池に向かって叫んだ。
「池の神様、ありがとう!」
小さくちぎったパンを撒くと、池の鯉たちが我先にと水面に集まって、バシャバシャと水面を叩いた。まるでリクに祝福の拍手をするかのようだ。
それにしても、誰がリクのプレゼントを池の底から拾ったのかは分からないままだ。あのとき、ここに居たのはリクと池の鯉たちくらいだったのに。
これが神様の力なのだとしたら、すごい。めちゃくちゃすごい。
「そうだ。池の神様の話、他の人にも教えてあげよう」
そう呟いた瞬間、例のハート模様の鯉がパンを追うのをやめてふとこちらに顔を向けた。
リクには、その鯉が大きく頷いたように見えた。
──ねえ聞いた? 鯉太郎の新しいアイディア。
──アイツ、また何か悪巧みをしてるの?
──今回は悪巧みじゃないよ。鯉太郎、学校の子供達の恋のキューピッドになりたいんだって。
──恋のキューピッドぉ? 鯉だけに?
──ほら、鯉太郎の背中の模様、ハートマークみたいでしょ。そこから思いついたって。
──ウチの池をパワースポットにするんだって。だから僕らにも協力してほしいって言ってた。
──協力したら何か良いことあるの?
──もちろんあるさ。子供達の恋が成就するだろ、そうしたら。
──そうしたら……?
──とってもおいしいゴハンが貰えるんだって!
誰もいない静かな学校の夜。校庭の隅の小さな池で、まるで噂話でもしているかのように数匹の鯉が頭を寄せ合っている。
そのうち一匹がぴょんと跳ね、その水しぶきを穏やかな満月の光が照らした。
そう。これらは全部、水面下の出来事。

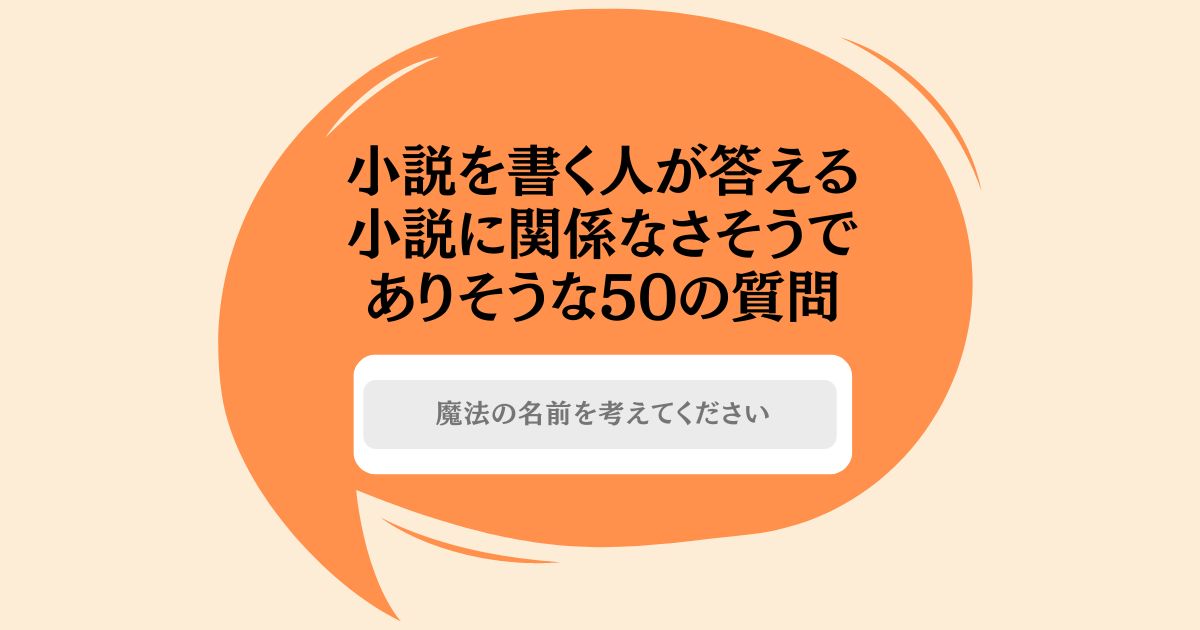

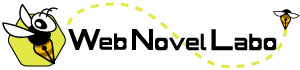


コメント